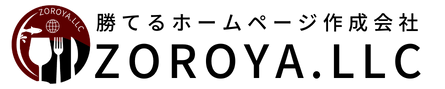※この記事にはプロモーションが含まれています
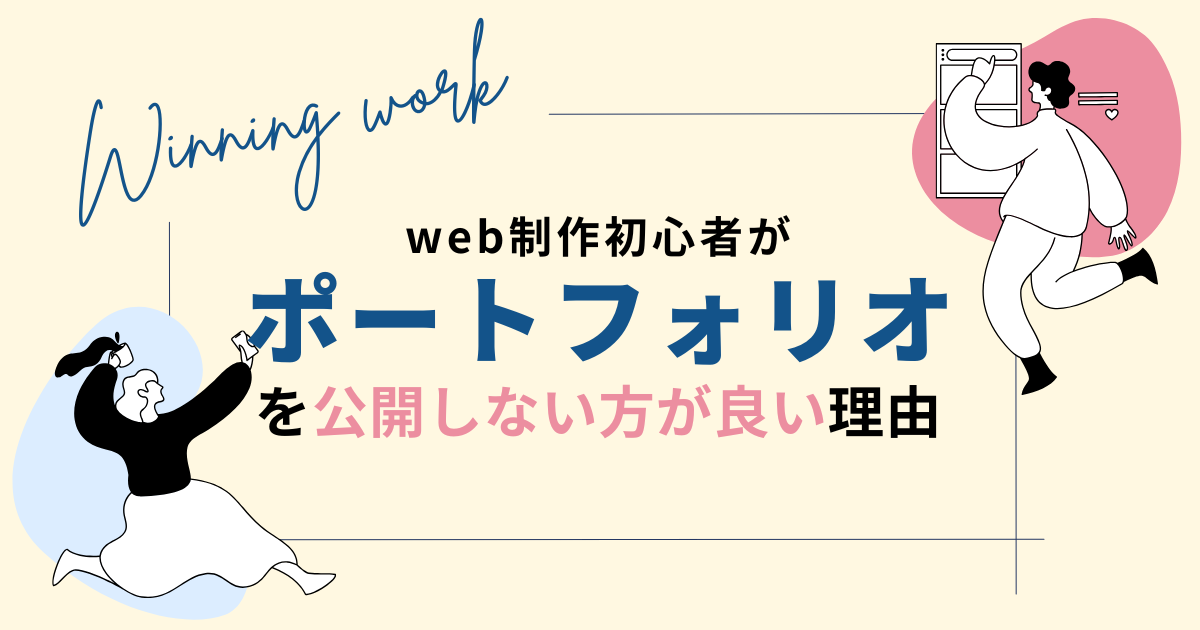
「ポートフォリオを作ったのに仕事が取れない…」
そんな悩みを抱えるWeb制作者やWebデザイナーは少なくないようです。でもこれは、あなたのデザイン力が原因ではありません。
というのも、僕自身ココナラでWeb制作ランキング全国1位を100回以上獲得し、400件以上のWeb案件に携わってきましたが、ポートフォリオを一度も公開したことがないんですね。それでも依頼が途切れないのは、ポートフォリオ以外の「判断材料」で勝負しているからです。
ポートフォリオは「成果に直結する情報」が欠けていると、クライアントにとって判断材料になりにくいんです。相手が知りたいのは「どんな課題がどう解決されるのか」。デザインだけではそこが伝わりません。
この記事では、初心者でも選ばれるために必要な、社会的証明の作り方・未来のベネフィット提示・専門性の絞り方をわかりやすく解説します。今日から使える「選ばれる戦略」を一緒に見ていきましょう。
ポートフォリオだけでは仕事が取れない3つの理由
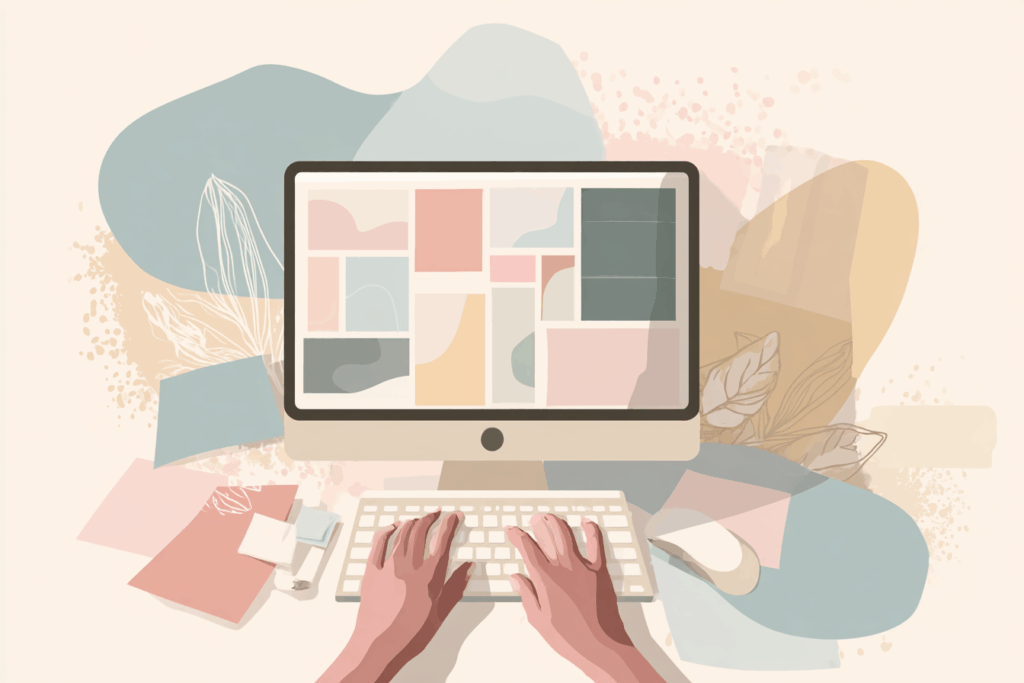
「ポートフォリオを公開しても仕事につながらない…」。
これは、あなたのスキル不足ではなく、「見せ方」の問題であることがほとんど。
多くの初心者が見落としているのは、クライアントが制作物そのものを評価しているのではなく、その裏側にある考え方や、ビジネス課題をどう解決できるかを見ているという点です。この視点を押さえるだけで、選ばれ方が変わってくるはず。
① デザインで比較されると初心者は勝てないから
ポートフォリオを公開しても仕事につながりにくい最大の理由は、デザインで比較される土俵に立ってしまうこと。
今はポートフォリオ作品があふれている時代なので、見た目だけで比べられると、初心者にとってはどうしても不利になりがちなんですね。
さらに言うと、どれだけデザインに関心があるクライアントでも、成果が出なければ最終的には不満が生まれるものです。事業を行っている以上、本人が自覚しているかどうかは別として、誰もが「結果」を求めています。
だからこそ、デザインだけを基準に提示してしまうと「見た目の完成度」が唯一の比較軸になり、経験値の高い制作者が優位に見えてしまいます。本来クライアントが選びたいのは、「成果につながる提案ができる人」。ものすごく突出したセンスの人がデザインで勝負するのなら勝ち目はありますが、多くの初心者にとって「ポートフォリオで選ばれる設計」では勝てません。
② クライアントは「課題解決力」を求めているから
クライアントが本来、確かめたいのは、デザインの良し悪しではありません。「自社の課題を解決できるのかどうか」。これがセンターピンです。経営者やオーナーなどは特に、数字の改善が最優先なので当然ですよね。
どれだけデザインに関心が強いクライアントでも本質的には変わらないはずです。成果が出なければ、初めはデザインに満足したとしても、いずれ不満が生まれるでしょう。繰り返しになりますが、事業をしている以上、本人が自覚しているかどうかは別として、誰もが潜在的に「結果(数字)」を求めています。経営者なら投資対効果を重視するのは当たり前で、利益に繋がらなければ、ホームページを作る意味がありません。
例えば、美容室オーナーであれば、経営数値の改善を最優先するため、デザイン単体では判断できず、「なぜそのデザインで成果が出るのか」という根拠を求めるようになるでしょう。意思決定の最終基準は「儲かるかどうか」ですから、デザインだけで判断材料を作ろうとしてもインパクトが弱く、結果として受注につながりにくくなるわけですね。
③ 制作事例は「戦略が違う複数ビジネスの寄せ集め」になりがち
もうひとつの問題は、「異なる前提条件の事例を並べると、戦略の一貫性がなくなる」という点。同じ美容室でも、以下のような諸条件によって、取るべき戦略は全く異なりますよね。
- 立地(都市・郊外)
- 客層(20代女性・ファミリー層)
- 価格帯(高単価・低単価)
- メニュー構成
こうした前提条件の違いが積み重なるほど、同じ美容室でも必要な戦略は大きく変わってきます。にもかかわらず、いきなり同業種の事例だけを見せると、クライアントは「このデザインで作ってほしい」と誤解し、あなたが本来提案すべき「戦略の軸」がズレてしまうことがあるんですね。
業種や条件が異なれば成果を出す戦略も変わります。クライアントは「自社でも同じ効果が再現されるか」を判断基準にするため、前提の異なる事例だけを見ても成果をイメージできません。
では何を見せれば受注につながるのか?答えは「社会的証明」
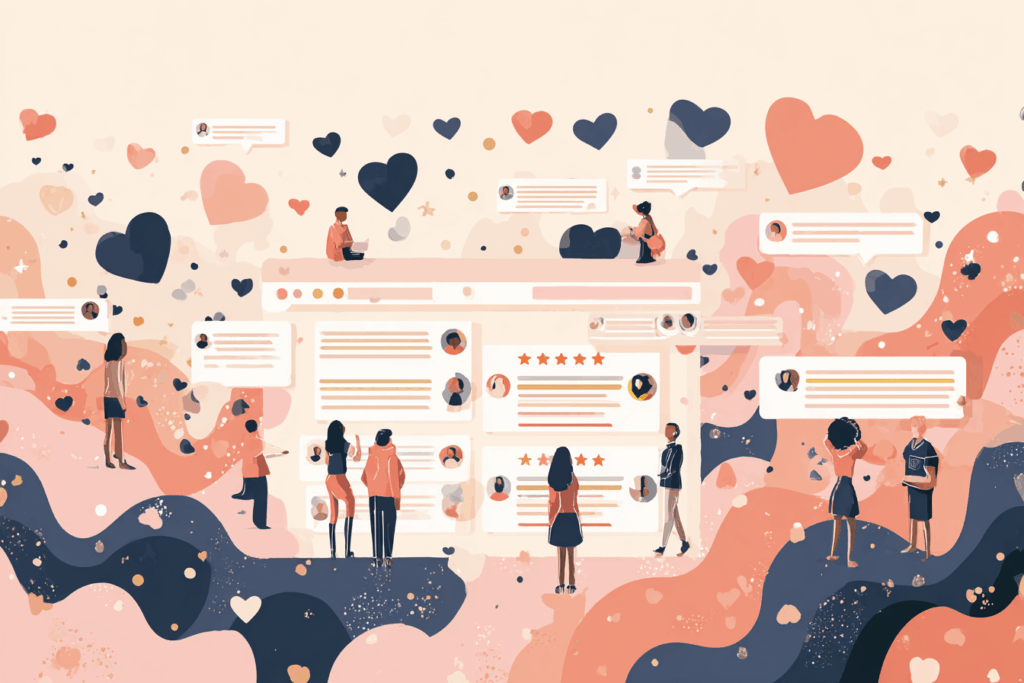
ポートフォリオの見た目だけでは選ばれにくい理由は、「クライアントが求めている判断材料」とズレているから。クライアントが本当に欲しいのは、安心して任せられる根拠です。それを最も強力に伝える手段が「社会的証明」なんですね。
ここでは、初心者でもすぐに取り入れられる社会的証明の活用方法を紹介します。
社会的証明とは?
社会的証明とは、「他の人が選んでいるから安心できる」という心理効果のことです。飲食店の行列やレビューが気になるのも、まさにこの働きですね。
Web制作においてもこの効果は非常に強力で、「この人なら信頼できそうだ」という判断を促す材料となります。特に、制作初心者や実績が少ない人にとっては、デザインよりも大きな武器になります。
なぜなら、社会的証明は件数の多さではなく「どんな文脈で成果が出たのか」という質的情報が評価されるから。そのため、初心者でも安心して提案できる強みになります。
ポートフォリオより社会的証明が強い理由
ポートフォリオよりも社会的証明が強力なのは、クライアントが本当に求めている判断材料が「安心できる根拠」だから。ここでは、その理由を3つに分けて紹介します。
デザインより「安心材料」で決断が進むから
クライアントは専門家ではないため、デザインの良し悪しだけでは判断できません。しかし、他者の声や数字があると「この人に任せても大丈夫」と確信を持ちやすくなります。
比較されにくくなるから
デザインは比較対象が増えますが、社会的証明は「その人固有」のものです。同じ土俵で争わずに済むため、初心者でも選ばれやすくなります。
戦わずして選ばれるポジションを取れるから
社会的証明は「差別化の武器」です。価格競争にも巻き込まれにくくなり、判断軸を「信頼」へと完全に切り替えられます。
社会的証明の力は本当に凄くて、初心者でも着実に積み上げればポートフォリオよりも有力な武器になります。デザインだけでは判断しにくいクライアントでも、他者の声や数字があると安心しやすくなります。同じ土俵で比較されにくくなる点も、社会的証明の大きな強みですね。
デザインだけで戦うのではなく、「信頼の土台をどう積み上げるか」という点が、受注につながる最大のポイントですね。
具体的に使える社会的証明の種類
社会的証明は広義で捉えるとさまざまな形があるので、初心者でも今日から取り入れられるはずです。
- お客様の声(実名・顔出し・動画は最強)
第三者からの肯定は、どんな営業トークより信頼されます。
- 口コミ・アンケート結果・星評価
ココナラやクラウドソーシングのレビューは非常に強力。
- 制作件数や数字実績
例:400件以上の制作経験・CV率UP・アクセスUPなど。
- プロセス・制作の流れを丁寧に公開
「どう進めるのか」が見えるだけで安心感が段違い。
※厳密には社会的証明といえないが、第三者視点で作るコンテンツとして加えておきます。
- Q&A(よくある質問)
問い合わせの心理的ハードルを下げるために有効。
※厳密には社会的証明といえないが、第三者視点で作るコンテンツとして加えておきます。
- Before→After、戦略・施策の説明と効果
「結果の根拠」が最も伝わる。
- 制作者本人の顔出し・価値観・ストーリー
属人性が武器になる個人制作者ほど効果が高い。
※厳密には社会的証明といえないが、第三者視点で作るコンテンツとして加えておきます。
どれもポートフォリオのような「見た目」や「雰囲気」といった感性や好みに依存するものとは異なり、信頼の土台を作るための材料となっている点を理解しておきましょう。
初心者でも勝てる!受注につながる3つの戦略

「ポートフォリオを見せても仕事が取れない」のは、初心者だからではありません。多くの場合、「見せる内容」と「判断される基準」が噛み合っていないだけなんですね。
だからこそ、クライアントが判断しやすい「課題解決の根拠」「未来のイメージ」「信頼材料」を揃えることが重要になります。ここでは、デザインで勝負せずに「選ばれる側」に回るための3つの具体的な戦略を紹介します。
① 「作品集」ではなく「問題解決事例」として見せる
すでにポートフォリオを公開している場合、初心者がまず見直すべきは「見せ方」です。クライアントは、ただの作品集では価値を判断できません。重要なのは、以下のような課題解決のストーリーなんですね。
- クライアントが抱えていた具体的な課題
- その課題に対して実際にどんな施策を行ったのか
- 施策の結果としてどのような変化や効果が生まれたのか
この「課題 → 施策 → 結果」を語れることが、最大の説得材料になります。ポートフォリオ事例だけでなく、これらをセットで伝えるべきでしょう。それができない場合は、公開しないほうが良いと思います。
また、評価の強さは以下の順で高まるため、理解しておくことが重要。
- 口コミ(声)
- 数字(成果)
- ストーリー(背景と文脈)
初心者でもこの3つを積み上げれば、ただの作品集より圧倒的に信頼性が増します。実績がゼロの場合は、まずは一つの業界に絞り、1件でも「課題 → 施策 → 結果」を明確に語れる事例を作ることが効果的です。
この1件を軸に「未来のベネフィット」を語れるようになるため、説得力も大きく高まります。
② 「自分のすごさ」ではなく「相手の未来」を提示する
多くの初心者がやりがちな失敗が、自分のスキルをアピールしすぎること。クライアントが本当に知りたいのは、「自社の課題がどう解決され、どんな未来が手に入るのか」という点でしょう。
つまり、スキルではなく「ベネフィット」を語ることが重要なんですね。
例:ホームページ制作で得られる未来
- 企業文化が明確になり、採用力が上がる
- 強みが整理され、競合との差別化が進む
- 顧客が選ばれる理由が言語化される
- リピート率が改善する導線が作れる
未来像が具体的に思い描けるようになると、クライアントはデザイン単体ではなく「期待できる成果」を判断軸にし始めます。結果として、価格勝負にも巻き込まれにくくなりますよ。
③ 「目に見えない信頼」をデザインする
最後に重要なのが、デザインスキルよりも「あなた自身の信頼性」をどのように見せるかという点。
例えば、信頼を高める要素には、以下のようなものがあります。
- 顔出し(人柄が伝わる)
- 経歴(どんな背景の人か分かる)
- 価値観(どんな思いで仕事をしているか)
- ストーリー(なぜWeb制作をしているのか)
制作会社は規模が大きくなるほど属人性が薄くなりますが、個人制作者はその「人柄」こそが最大の武器。SNSやブログでストーリーを発信するだけで、「この人にお願いしたい」「応援したい」という相談が来るケースは多くあるんですね。
実績が少なくても、信頼を見える化できれば選ばれることは十分に可能です。
初心者こそ「専門テーマ」を絞るべき理由
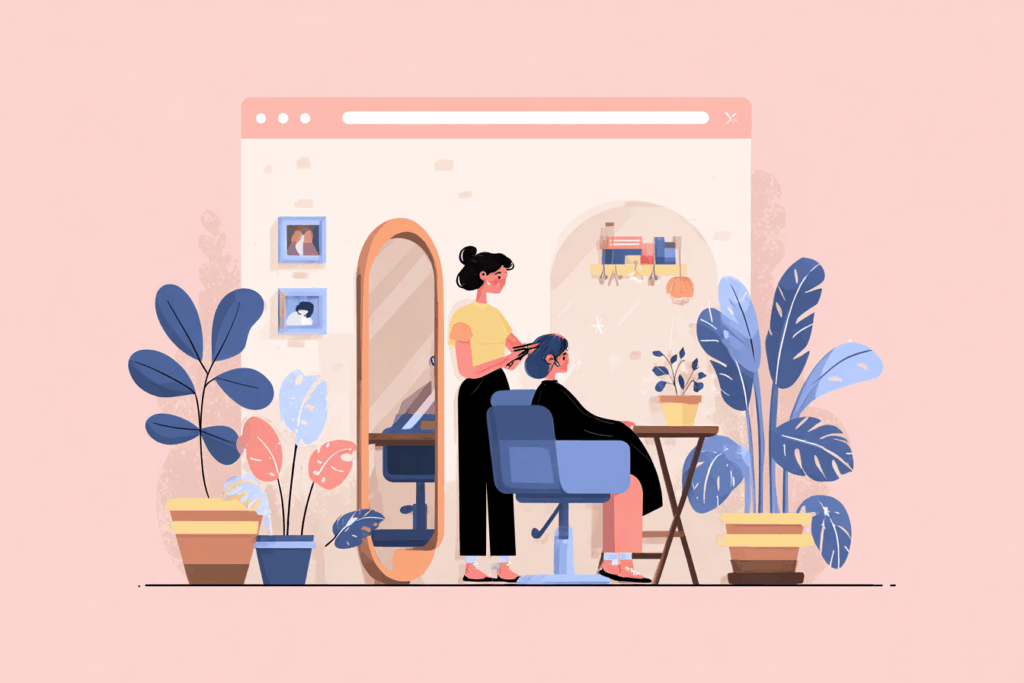
「実績がないから選ばれない」と感じている初心者ほど、「間口を広げすぎている」ことが多いかもしれません。マーケティングの理解が浅く経験に乏しい人が、どのような業種でも受けようとすると、クライアントの課題を浅くしか理解できず、競合との差別化もできません。
実績が少ない段階だからこそ、専門テーマを絞ることが有力な手段のひとつとなります。ここでは、その理由と具体的な見せ方を解説します。
分野特化すると信用が跳ね上がる
専門テーマを絞る最大のメリットは、クライアントからの信用が一気に高まることです。例えば、美容室専門に絞って「オーナーの悩み」「課題」「痛み」を調べてみると、以下のようなことがわかってくるでしょう。
- リピート率・新規集客・人件費・口コミ対策といった美容室経営者の悩み
- 業界特有の強み・弱み
- 年齢・性別・地域性といったターゲット毎の戦略
- 店舗型ビジネスならではの導線設計
業界特有の悩みや課題を深く理解していると、「この人は自分の状況を正確に理解してくれそうだ」という「事前の期待値」が上がるため、初対面でも信頼を得やすくなります。その結果、「指名買い」が自然と起きるようになります。
特に初心者は広く浅くではなく、狭く深くのほうが戦いやすい場合があります。
実績が少なくても専門性の見せ方は作れる
専門分野の実績が少なくても、専門性を演出する方法はいくつもあります。
- 専門テーマに関するコラムを書く
美容室なら「リピート率改善のポイント」「メニュー構成の見直し」など、課題に寄り添った記事を書くことで、業界理解の深さが自然と伝わります。
- 業界の課題を深掘りする
ターゲットの悩みをひたすら調べるだけでも差別化になります。「クライアント以上に業界を知る」姿勢が信頼を生みます。
- SNSで専門分野に特化した発信
X(旧Twitter)で専門領域に絞って発信するだけで、「この人は〇〇の人」という認知がつきやすくなります。
- 実績1件でも武器になる
専門性は「量」より「質」です。1件だけでも、課題→施策→結果 を深く語れる事例があれば十分です。
- 対談動画を撮る(最強メソッド)
専門家・事業者・オーナーと対談すると、「深い知識」や「本音ベースの理解」が自然と伝わります。実績が少なくても、一気に専門家として見られるため、講座でも強く推奨している方法です。
ポートフォリオを大量に用意しなくても、「この分野ならあなたが一番詳しそう」と思ってもらえる状態にすれば、仕事は取れます。
成功する初心者がやっている行動習慣
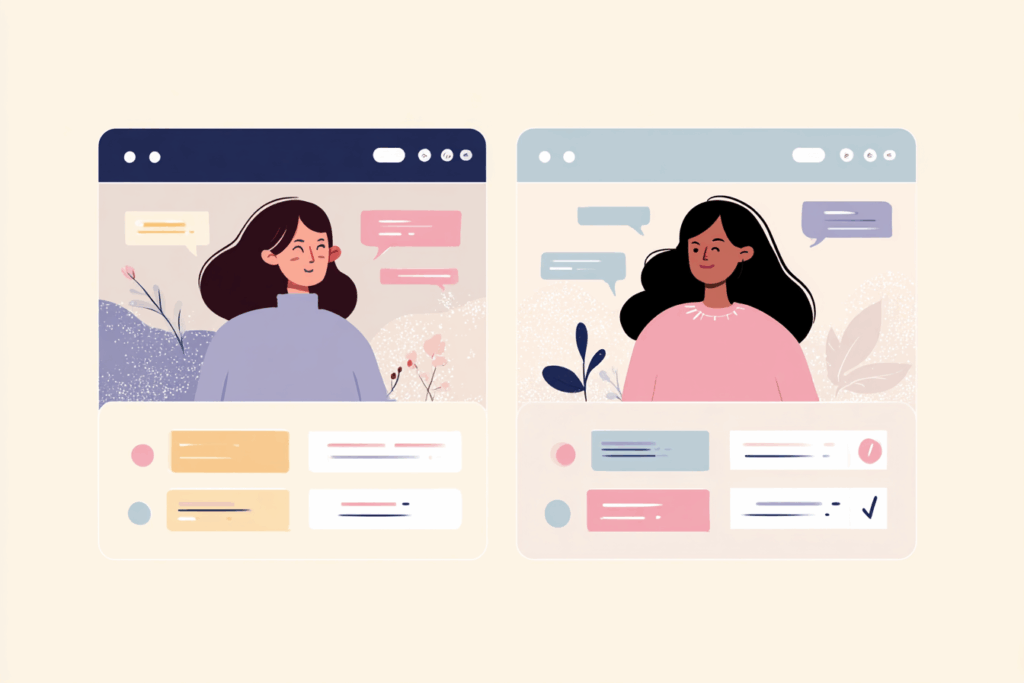
当社では、一部の方に「勝てるホームページ作成講座」を提供しています。そのなかで感じるのは、成果が出るのが速い方ほど、難しいテクニックより「行動習慣の質」を大事にしているということなんですよね。
専門スキルよりも、こうした質を押さえるだけで結果が大きく変わっていきます。ここでは、僕自身がこれまで実践してきた方法も交えながら、実際に成果を出している受講生が行っている習慣を、まとめて紹介します。
① ヒアリングを深く丁寧に行う
『勝てるホームページ作成講座』ではもっとも重視しており、受講生にも必ず実践していただいているのが、この 「ヒアリングの深さ」 です。デザインより前に、まず、相手の課題を正確に把握することが、実は成果を大きく左右するんですよね。
例えば、
- どんな悩み、課題、問題があるのか
- なぜ今サイトを作りたいのか
- 最優先で解決すべき課題は何か
- 競合はどんな状態か
- マーケットの中で自社はどんな特徴があるのか
こうした背景を丁寧に聞きとることで、提案の精度は一気に跳ね上がります。むしろ、ここを押さえられるだけで「この人は信頼できそうだ」と感じてもらいやすくなります。
どうやってヒアリングを深めるのか、については、別のノウハウが求められますが、その質が差別化ポイントになりうるので、ぜひ意識してみてください。
② 制作プロセスを見える化して安心感を与える
実績の少ない初心者が選ばれにくい原因のひとつは、「何をしてくれるのか見えない」という安心材料の乏しさゆえです。だからこそ、プロセスの見える化はしておきましょう。
- いつ何をするのか
- どんな流れで進むのか
- どこで確認が入るのか
- どのくらいの期間が必要か
これを明確に提示するだけで、安心感が格段に高まります。
③ SNSでのストーリー発信
SNSが上手な方は、自分のストーリーを発信することで、「スキル」そのものへの信頼より、個人への信頼が上回って受注につながるケースがあります。
- なぜWeb制作を始めたのか
- どんな価値観で仕事をしているのか
- どんな工夫をしているのか
担当者が固定されない制作会社では難しいですが、個人で活動していると、ストーリーを通して「人柄」を伝えることができます。SNSの使い方にもよりますが、この点は個で勝負できる今の時代ならではの信頼獲得のあり方ですね。
④ 提案文で未来のベネフィットを提示
営業メールや、DM、FAXなどで受注を狙うケースがあります。あるいは、ココナラやランサーズなどクラウドソーシングサイトでは、公開案件に応募する場合、クライアントに向けて効果的な提案ができれば、それに越したことはありません。
この際も大切なのは、自分のスキルをアピールすることではなく、「依頼後にどんな未来が手に入るのか」 を具体的に示すこと。初心者にありがちなNG例とともに、改善事例を以下に挙げておきます。
- NG例
「WordPress構築ができます」
- OK例
「集客導線を整理し、リピート率が上がるサイト構築をご提案します」
媒体によって、こんな風に一言を変えるのも効果的です。
- ココナラ・ランサーズの提案文
「同業クライアントで成果が出た導線設計を踏まえて、ご希望に合わせた改善提案を行います」
- 企業への営業メール
「自社の強みを整理し、採用・集客の成果につながるサイト構成をご提案します」
- DMやポートフォリオ送付時
「課題を踏まえた改善ポイントを事前に可視化し、制作後のイメージをつかみやすくする資料もお作りします」
クライアントが得たいのは、ホームページではなく、ベネフィット=明るい未来。それをイメージさせることで、「この人に頼むと良い方向に変わるかもしれない」と心理的な安心感につながるんですね。
⑤ 勝てる領域=比較されにくい土俵で勝負している
うまくいく人は、デザインやスキルで勝負しません。代わりに、以下のような「比較されない基準」で戦っています。
- 専門テーマ(美容室・整体院・士業など)
- 社会的証明(口コミ・数字)
- ストーリー・価値観
- 丁寧なヒアリング
- 制作後のサポート方針
- コピーライティング
- 人間力
これらは、再現しづらい属人性の高い要素であるため、ポートフォリオのように単純比較の対象になりません。その結果、価格勝負やデザイン勝負ではなく、「あなたにお願いしたい」という動機が生まれます。
まとめ|ポートフォリオより「信頼づくり」が受注の近道
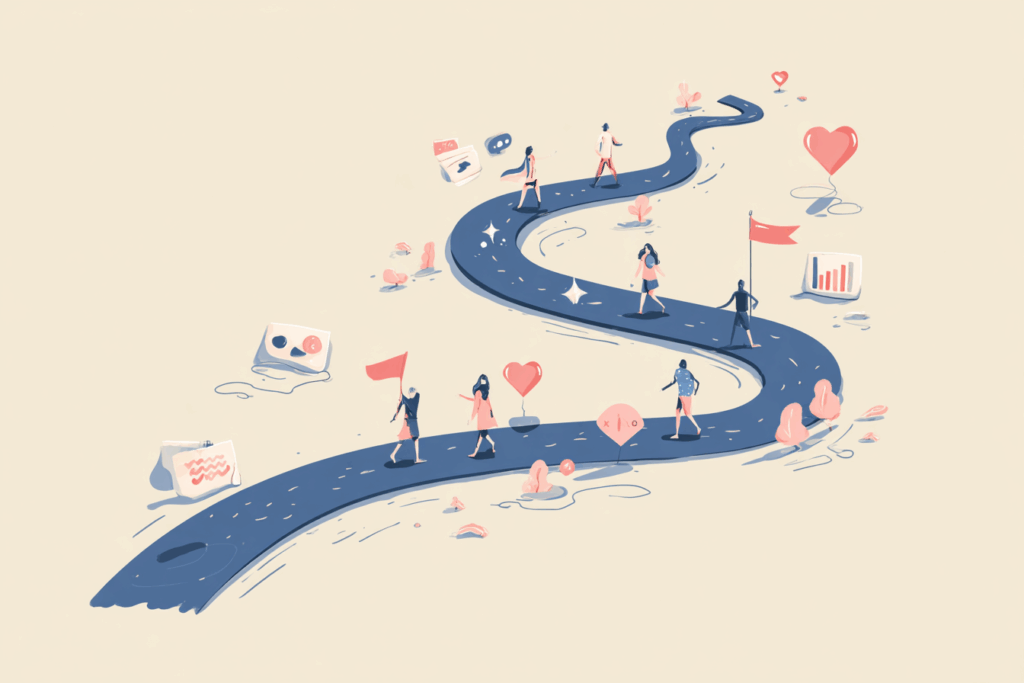
ポートフォリオを公開しても仕事につながらないのは、デザインのクオリティではなく、クライアントが本当に知りたい「判断材料」が伝わっていないことが原因。同じ悩みを抱える初心者は多いですが、これは単純なスキル不足ではないので、視点を変えることを強く推奨します。
クライアントが求めているのは、自社の課題を解決してくれそうだという確信。ベネフィット=明るい未来を提示し、あなたの価値観や専門性を伝えることで、信頼性が増し、初心者でも十分に選ばれる存在になれるでしょう。
こうして信頼残高というものを積み重ねて、見える形にしていけば、受注の流れは確実に変わります。まずは今日できるひとつの行動から始めてみてください。その行動のひとつひとつが、ポートフォリオ公開よりも安定する受注につながります。