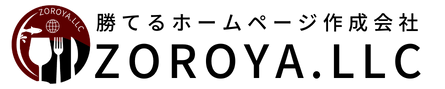※この記事にはプロモーションが含まれています
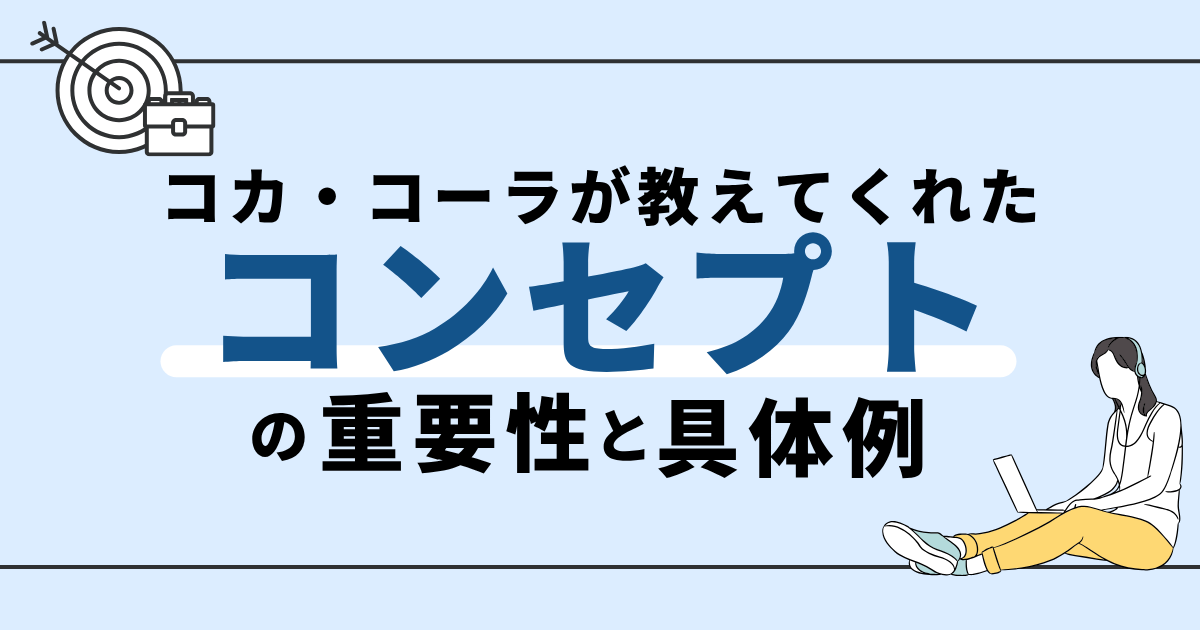
「あの人の商品は、なぜいつも売れるんだろう?」
同じような商品なのに、なぜか一人勝ちしている人っていませんか?スキルも経験も、あなたと大差ないはずなのに…。
その秘密はもしかしたら「商品そのもの」ではなく「マーケティング・コンセプト」にあるかもしれません。
今から130年以上前の1886年、ある薬剤師が作った頭痛薬が、たった一つのコンセプトの転換で世界を席巻するブランドに変貌した話をご存じですか?
その商品こそが「コカ・コーラ」です。
もしあなたが「商品は良いのに売れない」と悩んでいるなら、この話は必ず参考になるはずです。
コカ・コーラは、もともと「薬用」だった

コカ・コーラはもともと薬用ドリンクであったことをご存じでしょうか?
マーケティング・コンセプトの良しあしが、「売れる・売れない」に直結するストーリーとして非常に参考になるので、ご紹介しますね。
薬剤師ペンバートンの挫折と挑戦
コカ・コーラが誕生したのは、1886年。生みの親は、ジョージア州アトランタで薬剤師のジョン・S・ペンバートン博士という人です。
ペンバートン氏は決して順風満帆な人生を歩んでいたわけではありません。1831年生まれの彼は、19歳という若さで薬学の学位を取得したものの、その後の人生は困難の連続でした。
南北戦争では南軍の中佐として従軍し、戦傷によってモルヒネ依存症になってしまいます。戦後、アトランタで薬局を開くものの、1872年に破産。建て直しを図りますが、74年と78年に火災に遭い、在庫の殆どを焼失するという不運に見舞われました。
当時の「売薬ブーム」という時代背景
ペンバートンがコカ・コーラを開発した19世紀後半は、アメリカで「売薬ブーム」が起きていた時代でした。医師不足から代替医療、殊に自然療法や万能薬が広く庶民に受け入れられ、薬剤師たちは自らの治療法や薬剤の売り込みに躍起になっていたのです。
高いばかりで効果が薄い従来の薬への不信感が高まり、市販薬である「売薬」に注目が集まっていました。売薬は誇大広告がはびこるものの、消費者にとって魅力的な選択肢だったわけです。
「奇跡の植物」コカの登場
そんな中、ペンバートン氏は頭痛薬の開発に勤しんでおり、1880年頃から「奇跡の植物」として注目を集めていた「コカ」に興味を示しました。
コカの葉には覚醒作用があるコカイン成分が含まれており、鎮痛や疲労回復の効果があるとされていました。当時、コカインは麻薬とは考えられておらず、「万能薬」として誰もが口にしていたのです。
最初にペンバートン氏が開発したのは、ワインにコカの成分を溶かし込んだ「フレンチ・ワイン・コカ」という薬酒だそうです。これはヨーロッパで大ブームになっていた「ビン・マリアーニ」という薬酒を模倣したもので、エジソンやローマ法王までもが愛飲したという伝説の飲料でした。
ペンバートン氏の「フレンチ・ワイン・コカ」には、さらにコーラの実のエキスも加えられていました。コーラは西アフリカが原産地で、コーラの実にはカフェインが含まれており、噛むと刺激作用があることから「魔法の薬」だと考えられていました。
アルコールとコカインが組み合わさることで、うつ状態を改善し、活力を与える薬として人気商品となり、「フレンチ・ワイン・コカ」は1週間で1000本近くも売れる大ヒット商品になったそうです。
禁酒運動という予期せぬ逆風
順調に成長を続けていた「フレンチ・ワイン・コカ」でしたが、1886年にアトランタとフルトン郡議会で「アルコール販売を禁止する法案」が採決されてしまいます。
当時欧米で巻き起こっていた禁酒運動が盛り上がりを見せ、ペンバートン氏が作ったアルコール飲料も非難対象となってしまいました。興味深いことに、当時コカインは麻薬とは考えられておらず、コカインより酒の方が問題視されていたという時代だったんですね。
「偶然」が生んだ炭酸コーラ
ペンバートン氏は禁酒中でも飲めるコカを使った飲み物を模索し続け、ノンアルコールのコーラシロップを開発しました。
そして、ここで有名な逸話が生まれます。通常ならば水で割って出す飲み物を、うっかり水と炭酸水をまちがって作ってしまったところ、これがとんでもなく美味しかったのです。
こうして1886年、現在のコカ・コーラの原型が誕生しました。
友人で経理担当のフランク・ロビンソン氏が「Coca-Cola」という名前を付け、あの有名なロゴも彼がデザインしました。名前は、使用していた2つの主要な原料「コカの葉」と「コーラの実」に由来しています。
薬用ドリンクとしてのコカ・コーラ
ペンバートン氏は多くの栄養機能表示を付け、「おいしくて、リフレッシュでき、スカッとして、爽快な薬用ドリンク」として市場に投入しました。特に「女性、神経衰弱や胃腸、腎臓の痛みに悩むデスクワーク従事者、神経強壮薬や刺激剤を必要とする者」等に効果があると宣伝されたそうです。
1886年5月29日付『アトランタ・ジャーナル』誌には、『Coca-Cola,DELICIOUS!REFRESHING!EXHILARATING!INVIGORATING!(コカ・コーラ、おいしく!さわやか!軽やかに!元気はつらつ!)』という初めての新聞広告が掲載されています。オロナミンCみたいですね。
実はペンバートン氏自身もモルヒネ中毒に苦しんでいたため、コカの葉を含むコカ・コーラを飲んで中毒をコントロールしようとしていました。そのため、コカ・コーラは当初、様々な効能の他に、モルヒネやアヘンの中毒の治療にも使えると宣伝されていたのです。
コカ・コーラが現在の地位を築いた理由
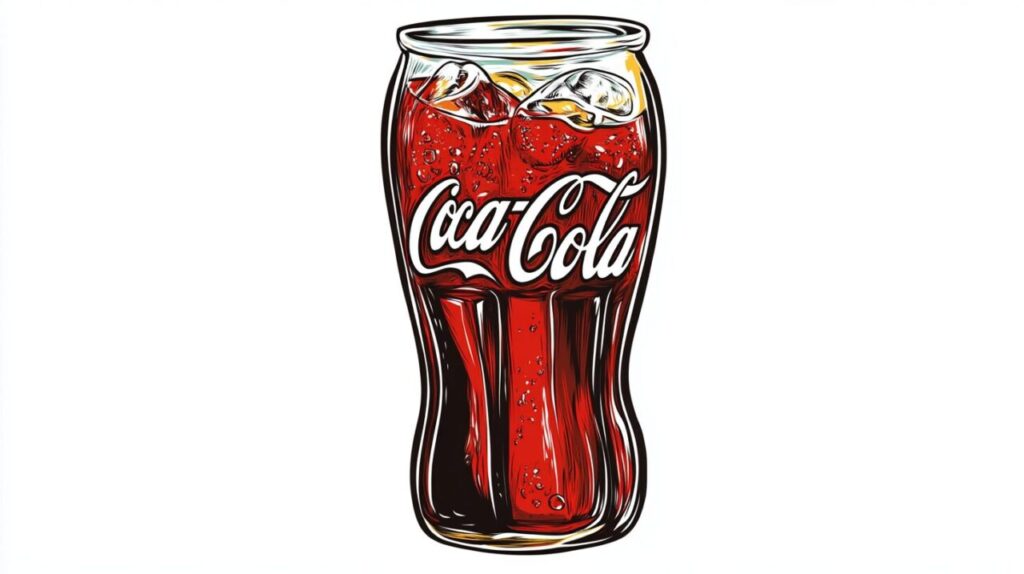
しかし、ペンバートン氏にとって事業は決して順風満帆ではありませんでした。
1887年に特許も下りて順風満帆に思えたこの事業でしたが、同年彼はコカ・コーラの権利を売却してしまいます。これに関しては「モルヒネを買う金を工面するため」や「息子のチャーリーが酒に酔って売ってしまった」など様々な説がありますが、真相はよく分かっていません。
その後も2重売却や文書偽造事件などごたごたが続き、結局、企業家エイサ・G・キャンドラー(後にアトランタ市長)がこの事業を引き継ぐことになります。その売却額はなんと、1ドル。噓でしょ?と思うような額ですが、たしかに1ドルだそうです。紆余曲折を経て、1888年、キャンドラー氏はペンバートン氏の息子らと共にコカ・コーラ・カンパニーを設立したのでした。
薬用ドリンクから、売れるコンセプトへの転換
エイサ・キャンドラー氏は1851年生まれの実業家で、後にアトランタ市長も務めた人物です。彼もまた原理主義的な教育を受けており、自分の考えを曲げようとしない頑固な一面もありましたが、ビジネス感覚に長けていたようです。
長くなりましたが、実は、ここからが、今回お話ししたい本題です。
キャンドラー氏がコカ・コーラを継承した当初は薬用ドリンクとして販売されていたのでした。しかし、キャンドラー氏は重要な気づきを得ます。
「薬として販売することには、効き目があるとされる諸症状を訴える者だけにマーケットを狭めてしまう」
この洞察こそが、コカ・コーラを世界的ブランドに押し上げた最大の要因といえるでしょう。キャンドラー氏は、薬としての背景が根強かったコカ・コーラを、「清涼飲料水」としてのプロモーションに方向転換したのです。
薬用ドリンクから、爽やかで、美味しい清涼飲料水へ
これは、まさにコンセプトの大転換でした。
ペンバートン氏は、あくまで、薬用にこだわっていました。ターゲット属性は、病気の人、疲れている人、自身のようなモルヒネ中毒の人などで、用途は症状緩和を訴求していたのです。そのため、消費者は、薬の効能を求めて、必要に迫られて購買に至りますし、利用シーンは、体調不良時に限定されます。
こうした文脈では、「さわやかで、びっくりするほど美味しい」コカ・コーラの一番良いところ=便益が活かせません。そこで、キャンドラー氏は、ターゲット属性を薬用という不要な縛りを開放して、コカ・コーラの強みを活かして、リフレッシュしたいときや、楽しい瞬間に楽しめる清涼飲料水として、リブランディングした訳です。
そして、革命的ともいえるのが、中身は全く同じでも、都会的でスタイリッシュな瓶に詰め替えて販売したこと。これが「爽やかで、美味しい清涼飲料水」のイメージ戦略を確固たるものにしました。
こうして、現在のコカ・コーラの躍進が始まったわけです。
コカ・コーラの視覚的ブランディングの工夫
もうひとつ、象徴的なエピソードをお伝えするべきでしょう。
1888年にエイサ・キャンドラー氏が「コカ・コーラ」の調合法を買収してコカ・コーラの事業も引き継いだとき、彼が工夫したことが面白い。シロップを運ぶ樽を全て赤く塗ったんですね。現在でもコカ・コーラのアイデンティティとして世界中に認知されている「コーク・レッド」はこのとき誕生しました。当時のアメリカにおいて、この刺激的な赤色は、アメリカ中を沸かせたと言われます。
コカ・コーラ社は今でも、ブランドの資産として大切にしており、「この赤い色を見れば誰もがすぐにコカ・コーラだと認知して頂ける」お客様の印象に残る色として活用しています。
なお、発売当初はコカインの成分が入っていたようですが、1903年以降、コカインの成分は安全性の観点から除去され、コーラの実自体も風味に殆ど影響を与えない微量となっています。
また、1906年にはFDA(食品医薬品局)との間でカフェイン含有量を巡る論争も起きましたが、最終的にはカフェインの含有量を半分にすることで和解しました。このような安全性への取り組みも、長期的なブランド価値の構築に寄与したと言えるでしょう。
商品を変えなくても、コンセプトを変えるだけで売れる可能性がある
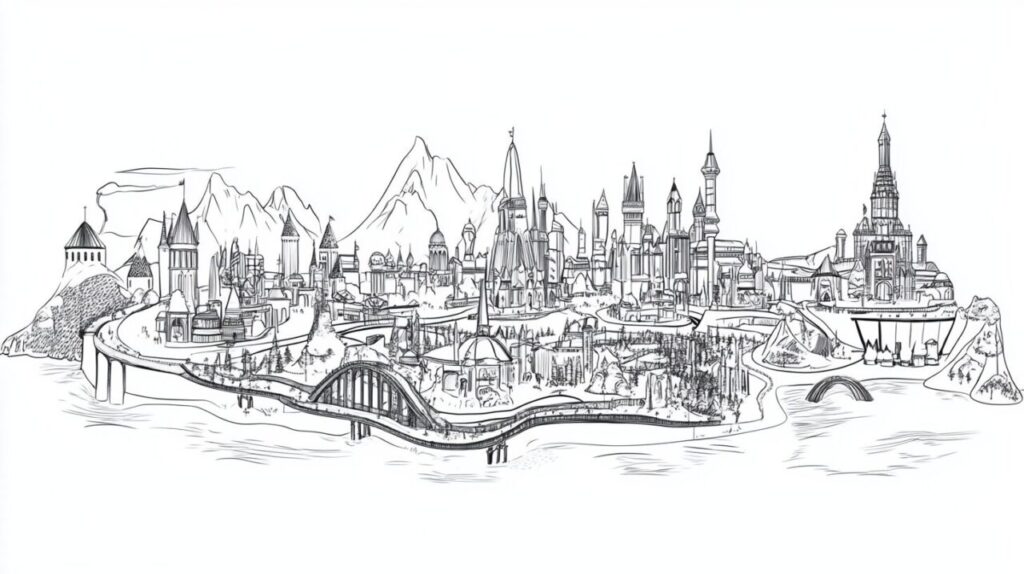
コカ・コーラの誕生ストーリーを聞いて、あなたはどう思いましたか?
僕はこの物語を知って、思い出したことがあります。USJをV字回復させ、業界のトップを走る東京ディズニーランドを一時的に集客数で抜くまでに成長させた、森岡毅さんは、こう言っていました。
選ばれる確率を増やす最大の鍵は、「コンセプト」である
USJがV字回復した最大の要因。それは、コンセプトの変換であると僕は認識しています。
USJがV字回復した最大の要因はコンセプトの転換
森岡さんが就任する前のUSJは「ハリウッド映画専門のテーマパーク」でした。しかし、それでは、数学的に明らかに絞り過ぎであることを、森岡さんは見抜きました。子連れファミリーがレジャーとして利用する理由になりづらかったし、中高生が友だち同士でワイワイ楽しむために来るレジャーとしても今ひとつ。大人が楽しめるテーマパークであったかもしれませんが、そのマーケットで勝負するには母体がでかすぎ、そして、USJが本質的に持っている、エンターテイメントを表現する技術が存分に活かされていなかった。
そこで森岡さんは、どんなコンセプトを打ち立てたか?それが、、、
世界最高のエンタメブランドを集めたセレクトショップ
映画好きの大人だけが楽しめるテーマパークではなく、家族もカップルも友達同士でも、USJに来たら絶対に楽しめる!というレジャーとして位置付けたのでした。
クリスマスの広告訴求を変更したり、小さな子供たちが遊べるエリアを新設したり、ジェットコースターを逆に走らせたり、漫画やゲームなど映画以外のエンタメコンテンツを投入し、莫大な費用をかけて目玉となるハリーポッターエリアを作ったり、さらにはほとんど費用をかけず、園内にゾンビを解き放つことでハロウィーン期間中の集客を激増させたりなど、やることなすことヒットさせてきた森岡さんですが、そのコンセプトの大変換が根底にあったのは間違いありません。
コンセプトを転換しただけで成長した、その他の事例
コカ・コーラや、USJだけではありません。従来のコンセプト、あるいは業界で通例のコンセプトから転換することで、事業成長してきた事例はたくさんあります。
スターバックスは、美味しいコーヒーを提供しているのではない
スターバックスは、ただ美味しいコーヒーを提供しているのではありません。
コンセプトは、家でも職場でもなく、自分らしくいられる空間=サードプレイス(第三の居場所)。この独自のコンセプトが、他の喫茶店と違う独自の空間を顧客に提供しているといえます。
僕も時おり、スターバックスで仕事したりしますが、たしかにコーヒーを求めに行くのではなく、気分転換をしに行っています。どこのお店も、店員さんの笑顔がいい。ドトールやタリーズに行くのとは違う雰囲気があるのは、そのコンセプトが活きているからでしょう。
富士フィルムは、自社の強みを再定義して再生した
富士フィルムは2000年代初頭、フィルムにこだわり過ぎて、デジカメのトレンドの波に乗り遅れ売上の6割、利益の7割を占めていたフィルム事業が4~5年で消失するという壊滅的危機に直面しました。同じくフィルム業界の巨人だったコダックが2012年に倒産する中、同社が奇跡的な復活を遂げたのは、よく知られています。
その秘密もまた、コンセプトの根本的転換にありました。
「フィルム技術」から「ライフサイエンス技術」へ
当時の古森重隆会長は、自社の保有技術を徹底的に棚卸ししました。すると、フィルム製造で培った技術群が、実は様々な分野に応用できることが判明したのです。
コラーゲン技術は化粧品に、精密塗布技術は液晶フィルムに、画像処理技術は医療機器に、そして化学技術は医薬品開発に。富士フィルムは「写真フィルムの会社」から「技術で社会の課題を解決する会社」へとコンセプトを大転換し、現在はヘルスケア事業だけで年間5000億円超の売上を誇り、グループ全体の22%を占めるまでに成長しました。
「じゃがりこ」が売れた理由
1990年代前半、カルビーは「かっぱえびせん」や「ポテトチップス」で成功していましたが、さらなる成長を求めて新たな挑戦を始めます。そこで生まれたのが1995年発売の「じゃがりこ」でした。
従来のスナック菓子の多くは袋入りで、手も汚れるし、カバンに入れると粉々になり、かさばります。子どものおやつ、というイメージも強かった。そこで、じゃがりこの開発チームは女子高校生がカバンに入れて持ち歩けるような、袋菓子ではない、カップ入りのお菓子を作ろうというコンセプトで開発を進めました。
その結果、持ち運びに便利で手が汚れず、食べやすいカップに入った「じゃがりこ」が誕生したのです。発売当初は、「固い、味がしない」など意見も出たそうですが、今や、年商350億円を超えるカルビーの看板商品となりました。
誤解を恐れず言えば、売れたのは「美味しいから」ではなく「持ち運びに便利で、手が汚れないから」なんですよね。
まとめ:コンセプトを変えれば、世界が変わる

コカ・コーラの事例から、商品そのものよりも、どんな文脈で何を語るかが重要ということがお分かりいただけたのではないかと思います。
当社でもクライアントに提供するサービスはもちろんのこと、自社事業においても、もっとも慎重に検討すべき事案が、マーケティングコンセプトです。森岡さんがおっしゃるように、それ次第で、選ばれる確率が大きく変わるのです。1億しか売れないか、10億売れるか、それとも100億売れるのではないか、すべてはその商品・サービスが持つ提供価値とコンセプト次第。
もしあなたが「良い商品なのに売れない」「なかなか思うように伸びない」と感じているなら、商品そのものを変える前に、コンセプトを見直してみてください。当社で意識していることは以下の通りです。
- ターゲットの定義は適切か?
- 消費者にとっての本当の価値を伝えられているか?
- 制限的な思い込みに縛られていにないか?
- より大きな市場に向けて語り直せないか?
あなたの商品・サービスも、まったく違う角度から語ることで、新しい可能性が見えてくるかもしれません。
ぜひ参考にしてください!