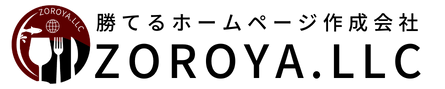※この記事にはプロモーションが含まれています

ビジネスの世界では「とにかく行動が大事だ」とよく言われます。たしかに、動かなければ何も起きない。行動すれば次の現実、という言葉を僕も大事にしています。ただ、やみくもに動けば成果が出る時代でもありません。
これは、野球のバッティングにも通じる話だなあ、と思います。バットを振ること自体は誰にでもできます。でも、ヒットを打つとなると話は別。ましてやホームランなんて、打てやしません。打席に立つまでに、相手投手の傾向や球種、守備の配置、自分の得意ゾーンなど、あらゆる情報を整理して“戦略を持って”スイングする必要があるでしょう。
マーケティングも同じです。広告を出す、SNSで発信する、セールスをかける。これらのアクションは「バットを振る」行為に近い。けれど、本当に成果を出す人たちは、その前段階——つまり「どういう球が来るかを読み、どう打つかを決めるフェーズ」に圧倒的な時間と労力をかけています。
勝負はバットを振る前に決まっている!
この原則を理解し、実践している人こそ、マーケティングで安定して成果を出し続けています。この記事では、野球のバッティング理論を軸に、成果を出すための“戦略型マーケティング”の極意を掘り下げてみたいと思います。
なぜ「打つ前」がすべてを決めるのか?—野球とマーケティングの共通点

僕は野球経験がありません。サッカー部でしたし、学生時代はむしろ、野球に興味はありませんでした。
しかし、大人になり、プロ野球を見るにつれて、その面白さにはまってしまった。最近の趣味は、バッティングセンターでいかに打率を上げるか、です。どうすれば、芯にあたるのか。空振りしないか。早い球を打つときのタイミングの取り方…。そういった試行錯誤をするうち、バッティング技術を磨いていくことは、マーケティングとよく似ていると気がつきました。
型がなければ再現性は生まれない
プロ野球選手がフォームを何百回も自身の映像を見て確認するのは、美しいスイングを目指しているわけではありません。打てるスイングを「再現」するためだといいます。一度のヒットに価値はない。重要なのは、毎試合、安定してヒットを打てる仕組みを持っているかどうか。
これは、マーケティングにもそっくりそのまま当てはまります。マーケティングは、感覚だけで売れるものではありません。LP(ランディングページ)の構成、オファー設計、広告文の書き方など、成果を出すための「型」がある。これを知らずに自己流で取り組んでも、成果は上がらないはず。再現性のないヒットでは、ビジネスも、打率も伸びません。
マーケティングにおいてもバッティングにおいても「型」は再現性を高めてくれます。つまり、勝てる確率を上げるための装置ですね。ただ、注意しなければならないのは、「型」を知っているだけで、ある程度の確率は高まるものの、人並み以上の結果を求めれば、自分の得意な勝ちパターンを持たないといけない。
バッティングに関して、僕はド素人です。下半身の動かし方や、バットの握り方などの基礎を学ぶことで、ボールに当てる確率を上げることはできました。でも、野球経験者のそれと比べると、明らかに打球の質が異なる。ひとことでいえば、しょぼいのです。そもそも音が違う。ここから先は、自分なりに言語化したり、自分が勝ちやすいパターンを、繰り返し練習することで見つけていく必要がある。
打席に立つ前の「読みと準備」が結果を分ける
プロ野球では、打席に立つ前にどれだけ相手を研究しているか。これを、専属のアナリティストの意見やデータを見ながら、打撃コーチと確認するといいます。アマチュアの野球ではそうではないかもしれません。しかしプロ野球選手のような、その道でトップレベルの選手でも、事前の情報を確認するのです。これも、マーケティングで言えば、ターゲットの行動心理をどれだけ深く理解しているか、ということでしょう。
「この人は今、何を欲しがっているのか」
「どんな言葉に反応し、どんな提案に心が動くのか」
「競合はどういうアプローチをしているのか」
これらの情報を読み解かないまま見切り発車すれば、空振りする確率は当然高くなる。相手のことがわからなければ、当然ですね。逆に、精度の高い“読み”を持てれば、ヒットの確率は格段に上がる。マーケティングも、おそらくプロのバッティングも、情報戦であり、準備の質がそのまま結果を左右する世界です。
偶然のヒットより、狙って打つルーティンを
「たまたまバズった」投稿や、「勢いで売れた」商品。一時的な成果は出るかもしれません。でも、それが続かないのがビジネスの現実。考えてみれば、バッティングも「たまたまあたった」としても、次も同じように売れるかわからない。
狙ってヒットを打てれば、いうことありません。では、狙って打つにはどうするか?
僕は、バッティングセンターに行って、一球でも多く、バットの芯にあてるため、Youtubeや本を見ながら、仮説をたてて、素振りをします。修正すべき点はどこか、それを改善出来たら、よくなるのかならないのか、その繰り返しで、徐々に結果が伴ってきました。
マーケティングでは、いわゆる、PDCAサイクルを回すといえるでしょう。仮説を立て、テストしてみて、改善しながらより精度を高めていく。偶然のヒットではなく、狙って打てるように軌道修正していくわけです。そうして、自分なりの「勝ちパターン」を見つけていく必要があります。
「戦略的なルーティン化」が、成果を安定させ、勝ち続ける基盤になると考えています。
マーケティングにおける「バッティング理論」の応用

バッティングを学べば学ぶほど、必要なスキルは「打つ」ことにないことがわかってきます。事前の準備、スイングを最適化する技術、タイミングを見極める判断力、それから最適なPDCAを回して軌道修正していく習慣。マーケティングにおいても、同じことがいえると、お伝えしてきました。
ここからは、もう少し細かく深堀りして、バッティングセンターで空振りばかりしていた僕が少しずつ、バットに当てることができるようになった経験から得た気づきをまとめてみます。
ターゲット(球種)を絞るから打てる
バッティングど素人の僕はいろんな球種を投げられたら、全く打てません。しかし、どの球種が来るかわかれば、対処法があります。バッティングセンターでは、球種や高さを選べるので、「自分が得意とするコース」に絞ってスイングすれば、打てる確率は上がる。
マーケティングも同じですよね。「誰でもいいから買ってほしい」というスタンスでは、誰にも刺さらない。ターゲットの定義を明確にし、提供価値をチューニングしながら、訴求ポイントを絞り込む。球種を絞るから、当てることができるのです。
たとえば「20代の副業サラリーマン」と「30代前半のフリーランス女性」では、伝えるメッセージが違いますよね。重なる部分もありますが、副業サラリーマンは月10万でよくても、フリーランスであれば月30万はすくなくとも稼ぎたいと考えるでしょう。相手を明確に想定すれば、訴求の質が一気に上がります。広く投げずに、狭く深く。その方が、確実にヒットが出る確率は上がります。
ただし、これはあくまで、WEB広告などを通して、反応率を上げるために必要な考え方。ビジネス全体で設計するときは不必要に絞りすぎると、成長を妨げることがあるのでご注意ください。
スイングを最適化すれば、少ない打数でも成果が出る
もうひとつ、バッティングをしていて、重要な気づきがありました。
当たり前かもしれないですが、フルスイングが常に正解とは限らないんですよね。バッティングセンターとはいえ、常に同じ球筋で来るわけではないですし、芯に当てるには、タイミングとフォームを調整し、最小限の力で確実に打つ技術が求められます。自分の好きなところに「来た!」と思ったら、フルスイングでいいかもしれませんが、下手くその僕はまだまだ、そんなレベルにありません。精度高く、芯にあてるには、せいぜい、8割ほどの力で振った方が良い。マーケティングにおいても、がむしゃらが正解とは限りません。
ブログ記事ひとつとっても、むやみやたらに更新するより、どのくらいの月間検索ボリュームがあるキーワードを狙い、競合はどんな記事を書いているのか調べて、どんなユーザーに向けて、どんな構成で投稿すればエンゲージメントが高まるかを検証してから投稿する。広告運用も同様。CVR(コンバージョン率)を上げるためのLP改善やA/Bテストの積み重ねが、「少ない打数で結果を出す」ための最適化にあたります。
ポイントは「質を上げることに集中する」という姿勢です。
「待つ」ことも戦略。タイミングの見極めが重要
偉そうにいえることではないのですが…、どんなに良いスイングでも、悪球に手を出せば凡打になります。プロ野球選手が「見極める力」を大事にしているのは、甘い球を確実に仕留めるため。野村克也監督の著書で、野球はミスが勝敗を左右すると読んだ記憶があります。打ち損じ、投げミスが、勝敗を分ける。バッター目線でいえば、投げミスを逃さず仕留めることが、打率を上げるのでしょう。
マーケティングでも、無理にセールスをかける場面ではない時にアプローチしてしまうと、逆効果になります。相手が「比較検討段階=そのうち客」なのか、「緊急性の高い段階=今すぐ客」なのかによって、何を伝えるかは変わります。タイミングを誤れば、せっかくの見込み客も離れてしまいます。
だからこそ、ファネル設計(売れる仕組み作り)は重要になってきますね。見込み客にとって、最適なタイミングでオファーをかけれるよう、関係づくりが求められます。売り上げ欲しさに、ついつい、性急になってしまうこともありますが、「今は振らない」という判断ができる冷静さを持つことで、ビジネスの打率もあがるのではないでしょうか。
まとめ:マーケティングも“勝負は準備で決まる”

マーケティングで成果を出す人は、バットを振る前にすでに勝負をつけにいっています。いかに振るかではなく、いつ振るか。どの球に対して、どんなスイングで挑むか。その“準備”にこそ、勝敗のカギがある。
今回、バッティング理論とマーケティングの類似点を通して、3つの本質をお伝えしました。
1つ目は「型を持つことの重要性」。自己流のスイングでは、再現性のあるヒットは生まれません。これは、LP構成やセールス導線においても同じ。売れる型を知り、自分に合ったパターンに落とし込むことが、打率を安定させる土台になります。
2つ目は「相手を深く理解する力」。相手ピッチャーのクセを読むように、見込み客の行動や心理を先回りして想定する。ターゲティング、ニーズ分析、競合調査といった“読みの精度”が、そのままマーケティングの打率を左右します。
3つ目は「焦らずにタイミングを待てるかどうか」。うまいスイングができても、悪球に手を出せば凡打になる。売上を焦って不用意にセールスをかけるのではなく、適切なフェーズで適切な打ち手を打つ。これは、ファネル設計やリードナーチャリングの真髄でもあります。
僕自身、バッティングセンターで空振りしながら、少しずつ芯に当てる感覚をつかんでいきました。やればやるほど、ただ振るだけじゃダメだとわかる。大事なのは、フォームであり、タイミングであり、仮説と検証、そして戦略でした。マーケティングもまったく同じです。
「とりあえず動く」から卒業して、「戦略を立てて仕掛ける」へ。
あなたのビジネスが、狙ってヒットを量産できるフェーズへと進んでいくことを願っています。バットを振る前の準備にこそ、すべての可能性が詰まっているのです。