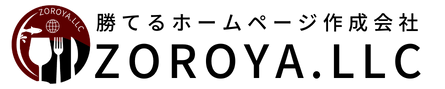※この記事にはプロモーションが含まれています
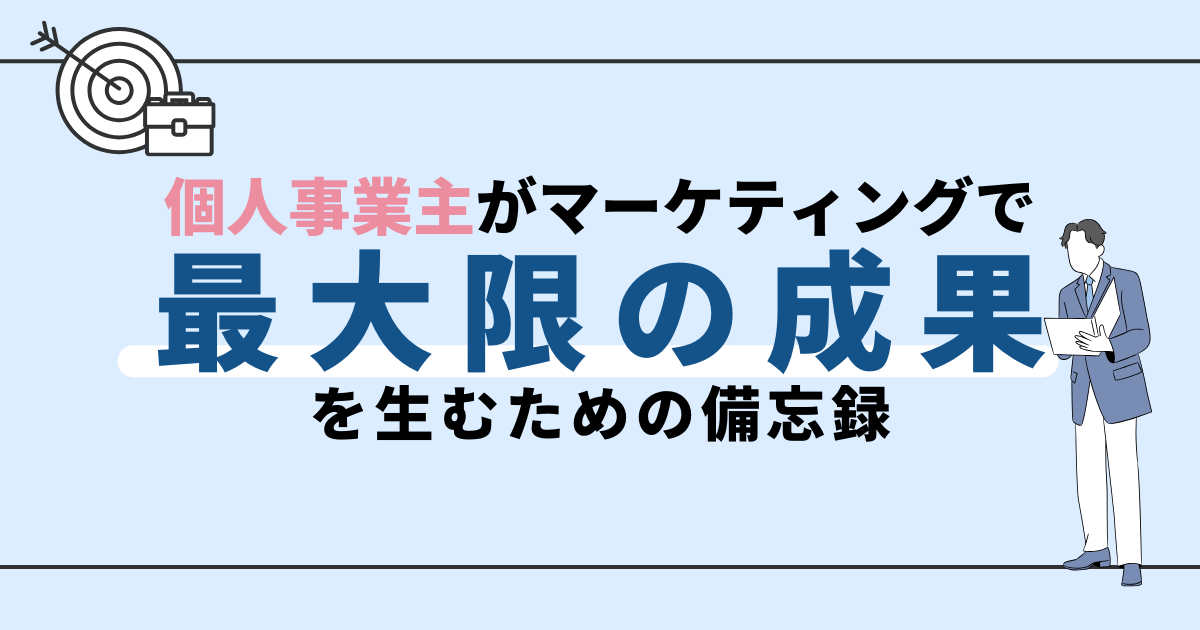
「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」
これは上杉鷹山の言葉として知られます。シンプルに解釈すれば「やればできる!できないのは、やらないからだ」ということ。
ちょっとスパルタ的な根性論はいってますが、僕のビジネス哲学の核となっていることは間違いありません。
ただ、マーケティングは、投資効率を考えるべきです。個人事業主のほとんどは、自分の労働が報酬となるビジネスモデルでしょう。考えるべきは、労働で得られる時間給と、最初は見返りが少ないかもしれないスキルへの投資を天秤にかけること。
時間給で考えれば、たとえば時給2,000円で1日8時間×月間22日働いたところで、352,000円。対して、スキルへの投資は最初は時給0円かもしれないが、1年後には時給10,000円になるかもしれない。時給1万円になれば、1万円×8時間×22日で、月間176万円です。
これが、未来に投資した時の可能性であり、マーケター的発想で成果を最大化させていくためのコツです。ここでは、個人事業主として時給を5~10倍に上げるための備忘録をまとめました。
マーケティング活動は、行動、検証、改善の繰り返しである
マーケティングは、単に商品やサービスを売る行為ではありません。
目標に向かって試行錯誤し、常に改善を繰り返すプロセスです。テスト(検証)を重ね、データや事実に基づいて戦略を調整し、最小の労力で最大の成果を得るために努力すること。これが、マーケティング活動の本質です。
だから僕は、世間の一般的なイメージと違い、マーケターは華やかな職業ではなく、めちゃくちゃ地味で大変な、泥臭い仕事だと思ってます。
トヨタの5S原則から、泥臭さを学ぼう
トヨタの5S原則は、僕がビジネスにおいて最も重視している原則の一つです。
整理・整頓・清掃・清潔・しつけ。それぞれの頭文字をとって「5S」。そんなことか、と馬鹿にしないでください。これは、単なる仕事をきれいにするテクニックではありません。ビジネスの効率化と品質向上に直結する哲学です。
この原則を取り入れることで、仕事の品質を高め、顧客への付加価値を創造できます。僕自身も10年前は、なんだそんなことか、と軽く考えていました。でも、仕事を深めていくと、仕事の基礎の大部分が含まれていることに気付き、自分の見識が浅かったことを恥じています。
【実践事例】レストランでの5Sの適用
仕事と趣味の大きな違いは、それによって賃金が発生するかしないかでしょう。ではなぜ賃金が発生するか?それは利益を生んだからです。では利益はどこからくるのか?付加価値を産み、その対価としてお客様から頂きます。
それと、5Sと何が関係しているか。
レストランであれば、清掃を欠いていると、お店として致命的です。また、整理・整頓ができていなければ、混み合ってきたときに、塩はどこへいった?レードルはどこおいた?など、たくさんの無駄が発生し、料理提供を遅らせてしまうかもしれません。お客様にとっては迷惑です。清潔さがないスタッフなんてもってのほか。嫌われます。
これらを全員が当たり前にできるようにしつけなければ、人はまとまりません。ルールなき組織は、滅亡するのも早い。各自が好き勝手やっている組織に、お客様は魅力を感じません。野球でもサッカーでも、チームを組むからこそ勝てるのであって、スタンドプレーがいくらよくても、負けるものは負ける。
5Sを徹底するだけで差別化できる
仕事もこの繰り返し。逆にこれらができるようになれば、逆のことが起こると思うのです。
お客様には好かれる。物を探す手間、無駄が減る。生産性が上がり、空いた時間はお客様の為に使える。よく整えられたスタッフ間の連携は、お客様を感動させることさえあるでしょう。これらがきちんと出来ているお店が少ないので、それだけで差別化できます。
特に、複数の人とチームを組んで働く場合、ものの定位置を定めることはとても重要です。
共有で使っているハサミがあるとします。使った人はまた使うからと、その辺においておくと、他に使いたい人がいた時に、困ります。まず、ハサミを探すところから動かなければならない。これを探すのに、20秒かかったとします。それが一日一回あれば、年間で2時間のロスです。これが3つも4つもあったらどうでしょうか?その時間を、お客様へのサービスにあてたり、料理の研究開発にあてたり、勉強の時間にあてたり、有意義に過ごせるものを、無にしてしまいます。
レストランの厨房でも、5Sは外せません。
マーケティングと5S
マーケティングとどんな関係があるのか?と思われたかもしれません。
僕は、レストラン経験が長かったので、マーケティングに対しても同じような姿勢で取り組むべきだと考えていました。マーケティング活動の本質は、行動、検証、改善の繰り返しにあるとお伝えしましたが、その地味で泥臭い作業の連続が、驚くような成果に結びつくことを知っています。
トヨタの5S原則は、ビジネスの効率化と品質向上を図り、顧客への付加価値を高めます。これは、仕事の基本を徹底し、常に改善を求めるマーケティングの姿勢そのものだといえるのではないでしょうか?
行動を起こし、その結果を検証し、必要に応じて改善を加える。この地道なプロセスこそが、個人事業主として成長するために欠かせないと考えています。
上杉鷹山に学ぶ、行動する量と幅がもたらす成果について
冒頭でも紹介した「なせば成るなさねば成らぬ何事も成らぬは人の為さぬなりけり」。上杉鷹山という人は、江戸時代、財政難と政治の汚職がはびこっていた米沢藩を立て直した偉人です。
やることやってれば、出来ないことはない。出来ないのは、やることやってないからなんだ。
自己責任、と言えばそうですが、見方を変えれば、すごく勇気をくれる言葉です。なぜなら「やればできる」から。壁にぶちあたっても、くじけないメンタルを保てるのは、この言葉のお陰かもしれません。必ず解決する方法があって、それを見つけられていないだけなのだ、と考えられる。
何事も行動に移すことで、可能性が広がります。だとしたら、その数が多いほど、チャンスは増えますよね。それでうまくいかなければ、確度を変えて幅を広げれば、成功するかもしれない。「成らぬは人のなさぬなりけり」というなら、なしてないことをするしかありません。
マーケティングでビジネスを成長させるためには、こうして失敗を恐れず、常に挑戦、あるいはテストする必要があります。この行動量の多さと、マーケター的検証、改善を繰り返していけば、成功しないことはむしろ、考えられません。そうですよね?
失敗を「ま、いっか」で終わらせないことの重要性
失敗を気にするな、と人を励ますときにいうことがあります。
しかしそれは、失敗を繰り返す人に対しては禁句です。僕自身「思考が浅い!」と上司から度々指摘されました。「表面しか見ていない」「それは対処療法であって、問題解決にはなってない」「もう一歩、深く考えろ!」「糞も味噌も一緒にするな」と。(汚くてスミマセン)
僕のような人間は失敗を「ま、いっか」で終わらせてしまうと成長できないんです。しかし長い間、思考が深いってどういうことか、わかりませんでした。もう一歩、深く考えろというけど、「できるだけ深く考えた結果なんだけど・・」と困ってしまった。
そんなときに出会えたのが著名な経営コンサルタント石原明さんの理論。
石原明さんに教わった、思考を深める方法
石原さんは、思考の深さには6段階あると話していました。上の3段階は左脳で考えられる領域。下の3段階は右脳で考える領域なんだと。思考の深い人は、浅い人に比べ、同じ景色を見ても気づくことが10倍以上違うんだそう。
では、思考を深めるにはどういうことをしたら良いのか?
石原さんは、思考を深めるには、なるべく同じことを、何度も何度も考えることが一番いいといいます。人は日々、ふらふらと、いろんなことを考えながら生きてます。それは脳の特性で、あっちこっち考えるようになっているんですね。
何度も何度も同じことを考えるというのは、実は脳にとって苦痛で、むしろ、新しい刺激がはいる方がラクなんだそうです。しかし、そうしてラクをした使い方をするところに深さは生まれない。「思考が深い!」とは、表面的な理解に留まらず、より深く物事を掘り下げることなんですね。
僕はこの理論を基に、一つの問題に対して何度も考えることで、新たな視点や解決策を見つけるよう努めるようにしました。これは、マーケティング戦略を練る上で非常に重要なアプローチだと思います。
失敗から改善への取り組みが、マーケティング成果を上げる
失敗をして、すぐに切り替えることは大事です。ひきずっていては、次の仕事ができません。でも「なぜ、失敗したのか」を深く考えもせず、次の仕事にうつってしまったら、同様の失敗をするかもしれない。
僕の場合はまさにそう。「ま、いっか」で済ましてしまうと、同じ失敗を繰り返してしまいます。そこで思考がストップしてしまう。
仕事の出来る人はそうしたミスを繰り返しません。石原さんも、なぜ失敗したのか、原因を突き止め、次に失敗しないためにはどうすれば良いのか、改善しなさい、と教えています。そうしていかないと仕事ができるようにならないと。「なぜ」を考えることで、思考は、もう一段、深くなる。
上司が「もう一歩、深く考えろ!」と叱ったのは、それを言いたかったのだと思います。
本の読み方で分かる思考の浅い人と、深い人
本の読み方も同じですね。
僕は、本を読んだ総量に関しては、同世代の人と比べて10倍以上読んでいる自負があります。でも、同じ本を何度も読んだ経験は少ない。次々と、新しいものを手に取ってきました。
たしかにこの読み方だと、本当に著者が書きたかったことや、真意に気づけないかもしれません。1か月も経って、内容を覚えているものは少なかった。それでは本を読む意味がない、と多くの先人は言います。
マーケティングも同様、効果が出ないからと言って、次々と新しい施策に手を出さず、なぜ、効果が出なかったのか原因をきちんと突き止めてから次のステップに進まないと、適切な選択をできません。下手をすれば、効果の出ない施策を形を変えて、同じようにしてしまう可能性がある。
お金も時間も非常にもったいないことです。
まとめ:マーケティング成果を最大化するために、実践している3つのこと
マーケティングは、行動、検証、改善の繰り返しです。それはとてつもなく、地道で泥臭い作業。
しかし、上杉鷹山の「為せば成る」精神を胸に、投資効率と労働のバランスを考え、失敗から学び、改善を重ねることが、マーケティングの成果を最大化するための必要だとわかりました。
僕が、そのために実践していることは以下の3つです。
- 引っかかったことについて、何度も何度も考える。
- 本を読んだら、どんな内容だったのか、どういう影響を与えてくれたか、まとめる。
- 失敗したら、原因を突き止め、繰り返さないように改善する。
あなたにとっても、何かのヒントとなればとてもうれしいです。