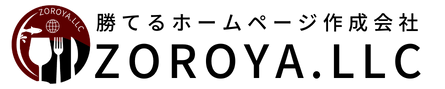※この記事にはプロモーションが含まれています
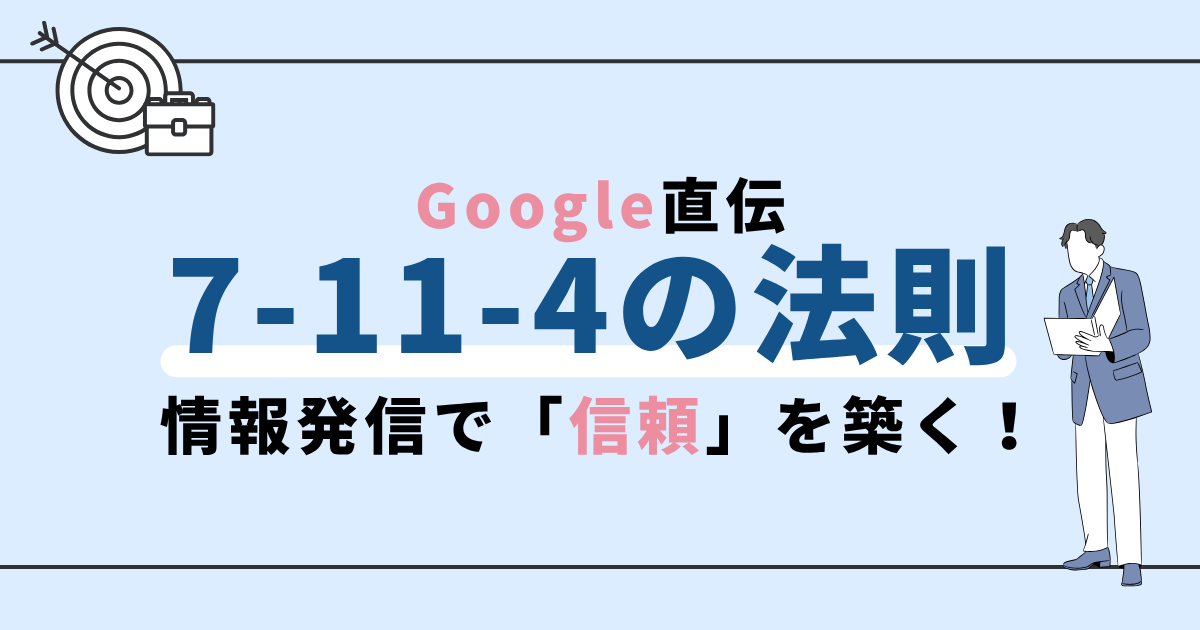
突然ですが、質問です。
あなたが初めて行ったレストラン。1回の訪問で「このお店、ずっと通おう」と心から思えるお店は、どれくらいありますか?
おそらく、あまり多くはないのではないでしょうか。ほとんどの場合、何度か通ううちに「やっぱりここがいいな」と思えるようになりますよね。
実は、これと同じことがWebの世界でも起きています。そして、Googleがこの現象を膨大なデータから分析した結果、興味深い法則を発見しました。
それが「7-11-4の法則」です。この法則を知ることで、なぜ、SNSやブログだけで発信し続けても成果につながりづらいのか、その理由がハッキリと見えてきます。
Googleが公表した「7-11-4の法則」とは何か?
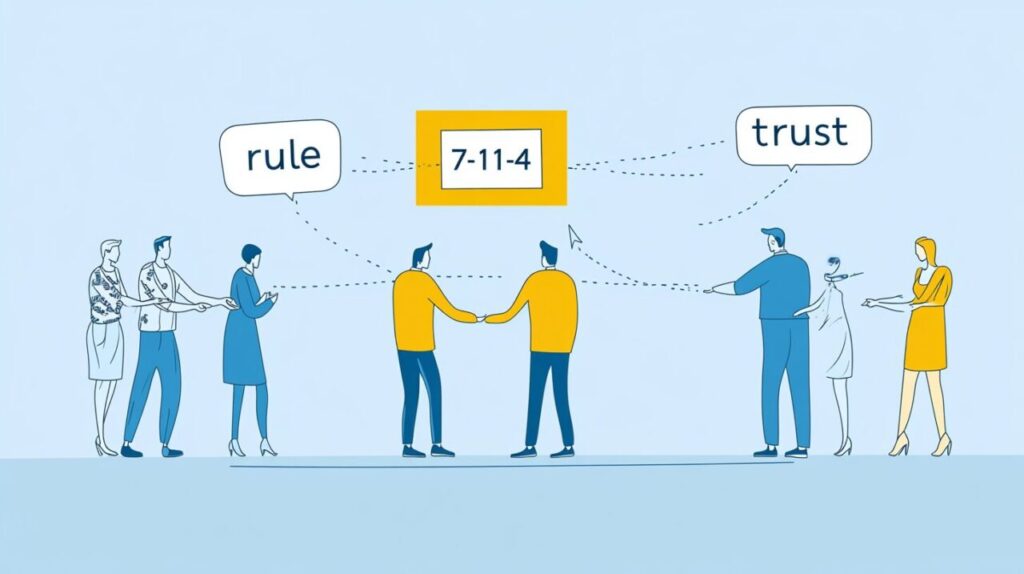
Googleが膨大なデータを分析して導き出したこの法則によると、人が「この人から買ってもいい」と感じるには、次の3つの条件を満たす必要があるそうです。
- 最低でも「7時間分」その人の発信を見たり聞いたりしている
- 合計「11回」以上、その人の情報に触れている
- 「4つ」以上の異なる場所で接点がある(SNS・ブログ・音声・動画・電子書籍・対面・広告など)
つまり、時間×頻度×接点の多さが、Webで売れるかどうかの分水嶺になるということです。これは仮説や憶測ではありません。Googleが行った消費者行動に関する研究に基づいていますので、参考になる指標ですよね。
僕自身も体験していた「7-11-4の法則」
この法則を知ったとき、「確かに!」と膝を打ちました。
実際に振り返ってみると、僕が商品を購入したり、サービスを利用したりしたとき、この法則に当てはまっていたからです。
尊敬する経営コンサルタント、石原明さんからの学び
たとえば、惜しくも亡くなられましたが、今でも尊敬している経営コンサルタントの石原明さん。
最初の接点は、Podcastでした。初めて聞いたときは、正直「何でも知った風な口をきく人だな」とほんの少し反発したものです。でも、自分とは見ている視点が全く違うことに驚かされて、それからぽつぽつと、通勤途中に聞くようになりました。
そして気づけば、「石原明」と検索して、ホームページを見るようになり、無料のメルマガにも登録。そこから、書籍を全部購入し、有料のPodcastや会員制勉強会のサブスクサービスも購入していました。当時は薄給の会社員でしたので、さすがに高額なコンサルティング依頼は出せませんでしたが、ほとんどすべてのコンテンツを買っていました。
振り返ってみれば、まさに「7-11-4の法則」通り。Podcast、ホームページ、メルマガ、書籍、4つの異なる接点を持ち、7時間以上の情報を受け取り、軽く11回以上、石原さんのコンテンツに触れています。そして、有料のPodcastや会員制勉強会のサブスクサービスの利用に繋がりました。
「7-11-4の法則」のエビデンスを求める
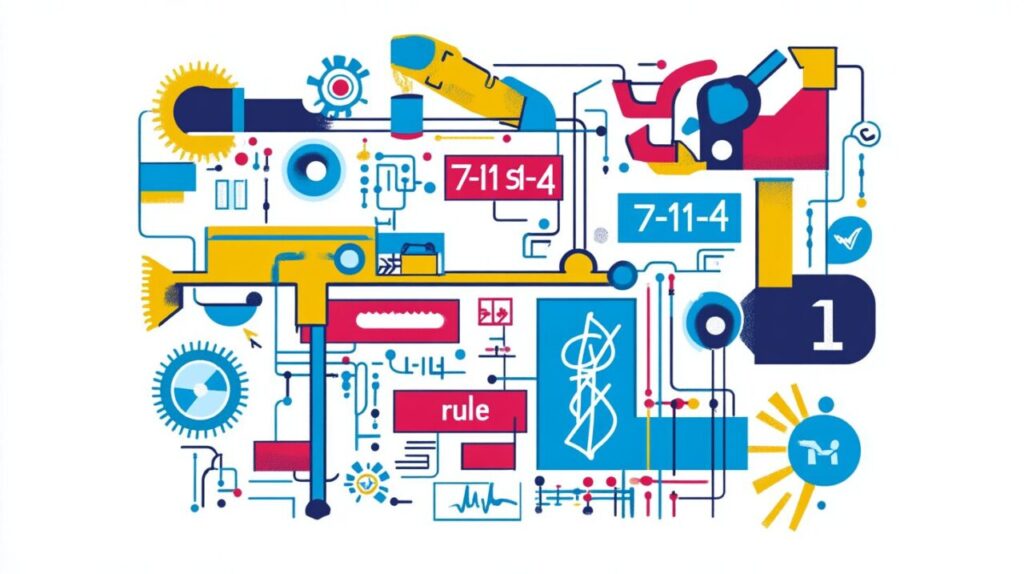
では、なぜこれだけの接触が必要なのでしょうか?
行動経済学や心理学のエビデンスから、「7-11-4の法則」が機能する根拠を見ていきたいと思います。
信頼構築には時間がかかる
行動経済学の研究によると、人間の脳は「損失回避バイアス」が強く働くようにできています。これは、利益を得ることよりも、損失を避けることを優先する心理的傾向です。
特にインターネットを介したビジネスでは、詐欺や悪質な商品への警戒心が高まっています。アメリカの調査会社Edelman Trustの2023年レポートでは、消費者の73%が「オンラインでの購入時に信頼できる情報源を複数確認する」と回答しています。
つまり、お金を払うという行為は、「この人なら大丈夫」「この人の言うことなら信じてもいい」という強固な信頼関係が前提になるのです。
記憶に定着するメカニズム
認知心理学の「エビングハウスの忘却曲線」が示すように、人間は情報に1回接触しただけでは、24時間後には67%を忘却してしまいます。
しかし、「間隔反復学習」の理論では、適切な間隔で情報に何度も触れることで、長期記憶に定着させることができると証明されています。
また、心理学者ロバート・ザイアンスが提唱した「単純接触効果(ザイオンス効果)」では、接触回数が10〜12回になると、好感度が最大化されることが実験で確認されています。11回という数字は、まさにこの科学的知見に基づいているわけです。
多面的認知で信頼度が向上
社会心理学の「認知的複雑性理論」によると、人は相手を多面的に認知するほど、より正確で安定した印象を形成できます。
メディア心理学の研究では、異なるメディアが脳の異なる領域を刺激することが分かっています。
- テキスト(ブログ): 論理的思考を司る左脳前頭葉を活性化
- 音声(Podcast): 感情や印象を処理する右脳側頭葉に作用
- 映像(動画): 視覚情報を統合する後頭葉と感情を司る大脳辺縁系を同時刺激
- 対面・ライブ: ミラーニューロンが活性化し、共感と信頼感が最大化
ただし、Googleの「7-11-4の法則」は、同じテキスト情報でも、たとえばブログと、X(Twitter)に触れることが異なる媒体としているので、上記4つの異なる属性のメディアが必要ということではありません。
いずれにしても、異なる媒体で接触することで脳の複数の領域から多角的にその人を理解し、より深い信頼関係を構築できるということはいえるのではないでしょうか。
情報発信において、多くの人が犯している間違い

この法則を知ると、情報発信において、多くの人が犯している間違いが見えてきます。実際に、僕のところに相談に来る方の90%以上が、以下のいずれかのパターンに該当しています。
SNSだけで完結させようとする
「Instagram頑張ってるのに、全然売れない…」
「Xを毎日投稿してるのに、問い合わせが来ない…」
「TikTokでバズったのに、売上につながらない…」
こうした悩みをよく聞きますが、SNSひとつだけでは「7-11-4の法則」を満たすのは困難です。
理由は明白ですね、「4つの異なる媒体」を満たせないからです。
それに、SNSは基本的に「短期集中型」のメディア。ユーザーは流し見をしていることが多く、一つの投稿に長時間をかけて向き合うことはほとんどありません。せいぜい、1~2分ではないでしょうか。
そう考えると、7時間分のコンテンツを提供するのは根気のいる話です。7時間分のコンテンツを満たすために必要な投稿数を、ざっと計算してみましょう。
- 140文字のツイート:読了時間15秒とすると、1680投稿必要
- Instagram投稿:平均滞在時間40秒とすると、630投稿必要
- TikTok動画:平均滞在時間30秒とすると、840本必要
あくまで試算ですが、根気よく続けたとしても、その人の専門性や人柄を深く理解するのは困難でしょう。断続的な短いコンテンツからでは、表面的な情報しか伝えられないからです。
コンスタントに継続できない
「11回以上の接触」を満たすには、ブログ、SNS、Youtubeなど異なる媒体での発信に加え、継続的な発信が求められます。情報には鮮度があり、プラットフォームごとのアルゴリズムがあるからです。特にSNSでは、ひとつの投稿が少しバズったとしても、他の投稿を見られることは少なく、時間が経てばすぐに埋もれてしまいます。運や偶然性を引き寄せるためにも、継続は欠かせないと言えるでしょう。
しかし、多くの人は以下、2つのパターンで、継続することができません。
1. 初期の過度な期待
多くの人が情報発信を始める際、短期間での成果を過度に期待してしまいます。
- 1週間投稿しただけで「なぜ反応がないのか?」と悩み始める
- 1ヶ月で問い合わせや売上を求めすぎて、結果が出ないと挫折する
- TwitterやInstagramで急成長した他人の成功事例と比較して焦る
- 「投稿すれば必ず反応があるはず」という根拠のない期待を持つ
しかし、7-11-4の法則を考えれば、最低でも7時間分のコンテンツを11回以上の接触で提供する必要があります。これは明らかに、数週間や1ヶ月で達成できるものではありません。
現実的には、週2回のブログ更新と毎日のSNS投稿を続けても、読者が法則を満たすまでには最低3ヶ月、多くの場合は半年以上かかるでしょう。
2. モチベーションの維持困難
継続の途中で、モチベーションを維持できなくなるパターンも非常に多く見られます。
- ネタ切れで投稿が止まる
最初は勢いで投稿していたものの、1ヶ月もすると「何を書けばいいかわからない」状態になる - 「いいね」や「コメント」の反応に一喜一憂
反応が少ないと「自分の投稿には価値がない」と思い込み、継続意欲を失う - 日々の業務に追われて後回しになる
クライアントワークや本業が忙しくなると、情報発信が最初に犠牲になる - 完璧主義に陥る
「質の高いコンテンツでなければ投稿してはいけない」と思い込み、結果的に投稿頻度が下がる - 他人と比較してしまう
フォロワー数や反応数を他人と比べて、劣等感から発信をやめてしまう
この継続の困難さこそが、多くの人が7-11-4の法則を満たせない最大の理由と言えるでしょう。実際に、僕のところに相談に来る方の中にも「最初は頑張っていたけれど、だんだん投稿が減ってしまった」と話される方が少なくありません。
コミュニケーションが一方的
これも非常に多いパターンです。情報発信を「一方的に伝える行為」だと勘違いしている人が少なくありません。
しかし、「7-11-4の法則」でも重要なのは「接触」です。これは一方的な発信ではなく、双方向のコミュニケーションを含むと考えた方が良いでしょう。ただ一方的な情報を垂れ流すだけでは、ユーザーとの「接触」は成立しづらくなります。
よくある間違った発信パターン
戦略により、一概にはいえないところもあるのですが、少なくとも情報発信をスタートするとき、以下のような発信は控えるべきです。
- 商品・サービスの宣伝ばかり
「新商品リリースしました!」「セミナー開催します!」など、売り込みメッセージが大部分を占める。読者にとって価値のある情報が少ない - 自分の成功談や実績アピールが中心
「売上○○万円達成!」「クライアントから感謝されました!」など、自慢話ばかりで読者が共感できない - 読者の悩みや質問に応えない
自分が話したいことだけを発信し、読者が実際に知りたい情報や解決したい問題を無視している - コメントや質問への返信をしない
せっかく読者からの反応があっても、返信せずに放置。これでは関係性が深まらない
ただし、一方的とはいえ、自社のお客さんになりうる属性に向けて、彼らの悩みや課題を知ったうえで、その解決の糸口となる情報発信を続けていくことは悪いことではありません。相手の立場にたっての発信は、本質的には双方向コミュニケーションに繋がると考えるからです。
要は、「この人は自分のことばかり話している」「自己承認欲求が強いんだな」と相手に感じさせない情報発信の設計をすべきということです。
数値目標だけに囚われる
「7-11-4の法則」を知った人の中には、数字だけを追いかけてしまう人もいます。法則の本質を理解せず、表面的な数値だけに注目してしまうパターンです。
当たり前ですが、内容の質を度外視して、7時間分のコンテンツを作成しても、それをすべて見てくれるとは限りません。仮に、コンテンツは7時間でも、10秒で離脱されたら、意味がないのです。
同様に、11回の接触という数字にだけ注目し、投稿の質やユーザーとの関係性を無視して、あらゆる媒体に投稿しても嫌われるだけでしょう。
これでは法則の本質を見失っています。「量」も重要ですが、それよりも優先すべきは「質の高い接触」です。
7-11-4の法則の真の意味
僕が解釈した「7-11-4の法則」の本質は以下の通りです。
- 7時間: ユーザーが発信者を理解し、信頼するのに十分な深い情報を提供する時間
- 11回: ユーザーの記憶に定着し、好感度が高まるまでの適切な接触回数
- 4つの媒体: 多角的に発信者の人柄や専門性を理解してもらうための多様な接点
数値はあくまで目安であり、本質は「ユーザーとの深い信頼関係の構築」にあるのです。
価値のないコンテンツを大量に作っても、かえって信頼を損なう可能性があります。「この人のコンテンツは薄っぺらい」「時間の無駄だった」と思われてしまえば、逆効果になってしまうでしょう。
むしろ、7時間かけてでも見たい・聞きたいと思える価値のあるコンテンツ、11回接触しても「また次も楽しみ」と思ってもらえる関係性こそが重要なのです。
「7-11-4の法則」を満たす戦略
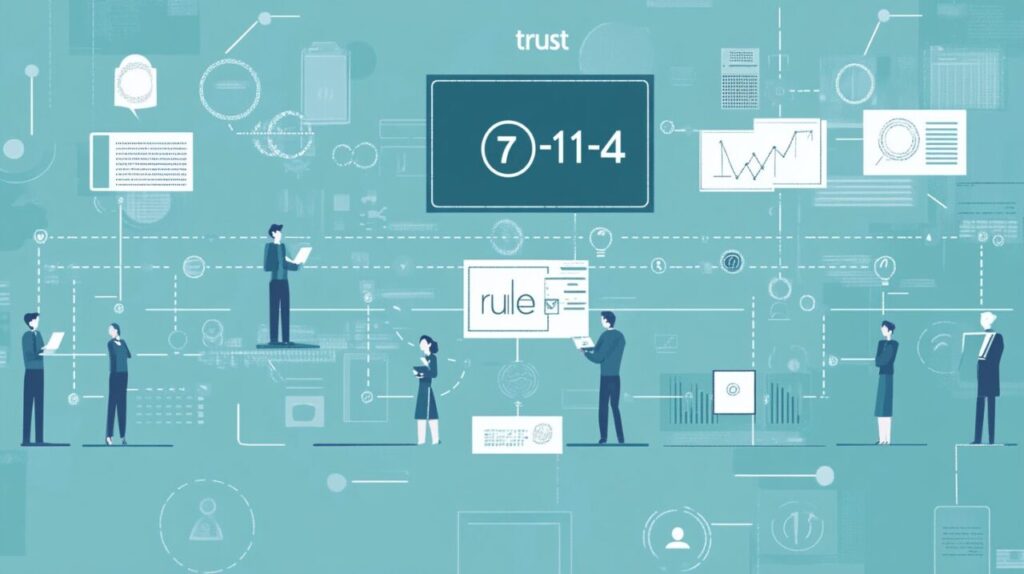
では、どうすればこの法則「7-11-4の法則」を満たすことができるのでしょうか?
それには、ここまでお伝えしてきた「間違い」を避けるのが肝要。「親指を描きたいなら親指を描こうとしてはいけません。親指を描くなら親指の周りの空間を描きなさい。」とアメリカの美術教師ベティ・エドワーズさんは教えるそうですが、つまりはそういうことです。
より実践的に活用いただくために、その条件について具体的にまとめてみました。
1. 4つ以上の媒体、プラットフォームを組み合わせる
まず、4つ以上の異なる媒体で発信することです。できれば、社会心理学の見地から、テキスト、音声、動画、対面と、属性の異なる媒体を組み合わせた方が効果的でしょう。また、ココナラやランサーズなどのクラウドソーシングサイトや、有料コンテンツ販売のプラットフォーム、それから、広告配信などもあわせて接触回数を増やすことをおすすめします。
それぞれの属性ごとにリストアップしてみましたので参考にしてください。
テキスト(読み物で伝える)
- ホームページ(ブログ)
- note
- 電子書籍
- X(旧Twitter)
- メルマガ・ニュースレター
- はてなブログ
- LINE
- DM
音声(耳から伝える)
- Spotify
- Apple Podcast
- YouTube Podcast
- Voicy
- stand.fm
- Audible
- Audiobook.jp
- Amazon Music
動画(視覚的に伝える)
- YouTube
- TikTok
- Instagram リール動画/ストーリーズ
- Facebook動画
- Vimeo
- Udemy
対面(リアルに伝える)
- リアルセミナー(会場開催)
- オンライン説明会
- 個別相談
- コンサル
- ワークショップ/講座
- YouTubeライブ / Instagramライブ / Facebookライブ
- オフ会/ファンミーティング
その他、コンテンツ販売プラットフォームや広告
- クラウドソーシングサイト(ココナラ、アランサーズ、クラウドワークスなど)
- Brain
- Tips
- クラウドファンディング(CAMPFIRE、makuakeなど)
- あらゆる広告
こうしてみると、たくさんありますね。もちろん、それぞれ攻略するのは大変ですが、相性の良い媒体に分散してコンテンツを作っていくことは、長期的にはリスクヘッジになると思います。
2. 長尺の良質なコンテンツを意識的に作り、そこに誘導する
短い投稿は“きっかけ”にはなりますが、信頼を構築するには長時間、滞在してもらうことが欠かせません。
前述のように、SNSのコンテンツが平均30秒程度で消化されるとすると、7時間分作成するのは840投稿が必要になりますし、この情報爆発時代に、継続・安定して見てもらうのは至難の業。ユーザーにとって、価値のあるブログ記事なら、読むのに30分かかるとしても、読んでくれるでしょう。もし、電子書籍を手に取ってもらえたら、消化するまでに2時間という時間を割いてくれるかもしれません。SNS投稿に換算すると240投稿分です。
つまり、多くの時間を費やしてもらうには、長尺コンテンツが不可欠なのです。時間が確保されれば、それだけ深くあなたの考えや価値観に触れてもらえます。「7-11-4の法則」において、7時間、という指標は一気に満たしてもらうものではありませんが、ファンになってもらうには、長く一緒に過ごしてもらうことが近道。
そうなると、自ずとコンテンツは良質であることが絶対条件になります。僕が長尺の良質なコンテンツ作成でおすすめするのは、電子書籍。5~10万文字で、体系立てて、相手が役立つノウハウ、スキルをまとめれば、1~2時間、そのコンテンツに接することになります。
実は僕も、電子書籍を軸として、長尺コンテンツを作成し、それをSNSや動画、音声に転用する仕組みを作ることで、効果と効率を最大化しようとしてきました。ご興味ありましたら、渾身の電子書籍をお楽しみいただけたら幸いです。
3. 継続的な発信を仕組み化する
「11回以上の接触」を満たすには、異なる媒体での発信に加え、継続的な発信が求められますとお伝えしました。でも、言うは易し行うは難し。当社でサポートしている会社様の中にも継続できなくて、せっかくの良質なコンテンツが埋もれてしまうことがあります。
発信スケジュールを決めることですが、そのコンテンツ作りに本業がおろそかになってしまっては本末転倒です。当社ではクライアント様のリソースや環境ごとにご提案させていただいていますが、比較的、導入しやすい仕組みは、なんといっても自動化。
まず、ネタとなるコンテンツを10個作ります。これは、基本的に、力技でこなすしかありません。気合です。難しければ、AIの補助を借りるのも一手。
その10個をベースに、SNS、電子書籍、音声、動画、メルマガ、と展開していきます。もし自社のリソースで難しければ、外注に出した方が良いでしょう。たとえば…
- ブログ:週2回
- SNS:平日毎日
- 動画:月4回
- メルマガ:週1回
これだけでも、月に20回以上の接触機会を作れますし、1-2時間分のコンテンツが作れるでしょう。
このあたりの仕組み化については、解説していくと膨大な分量になるので、また別の記事でご紹介したいと思います。
4. 異なる側面を見せる
当社で工夫していることをご紹介しますね。同じネタであっても、各媒体でまったく同じ内容を繰り返すのではなく、媒体に応じた異なる側面を見せることが反応を高めるコツだとわかってきました。
- ブログ:
専門的な知識や深い考察をじっくりと読んでもらうのに適しています。事例やデータを用いて、あなたの論理的な思考や分析能力をアピールしましょう。 - SNS:
日常の気づき、学習の成果、パーソナルな一面、あるいは速報性の高い情報を発信するのに最適です。親しみやすさや人間味を伝え、フォロワーとの距離を縮めます。 - 動画:
実践的なノウハウやチュートリアル、あるいは動きを伴う情報を見せるのに長けています。視覚と聴覚に訴えかけ、より記憶に残りやすいコンテンツを提供できます。 - 音声:
移動中や作業中など「ながら聞き」で利用されることが多いため、あなたの価値観や哲学、あるいはストーリーテリングを通じて、共感や信頼を深めるのに役立ちます。
こうした媒体の特性別の発信をすることで、ユーザーは多角的にあなたの魅力や専門性を理解し、より深い信頼関係を構築できるようになると考えています。まさに、多面的認知による信頼度向上が期待できるわけですね。
まとめ
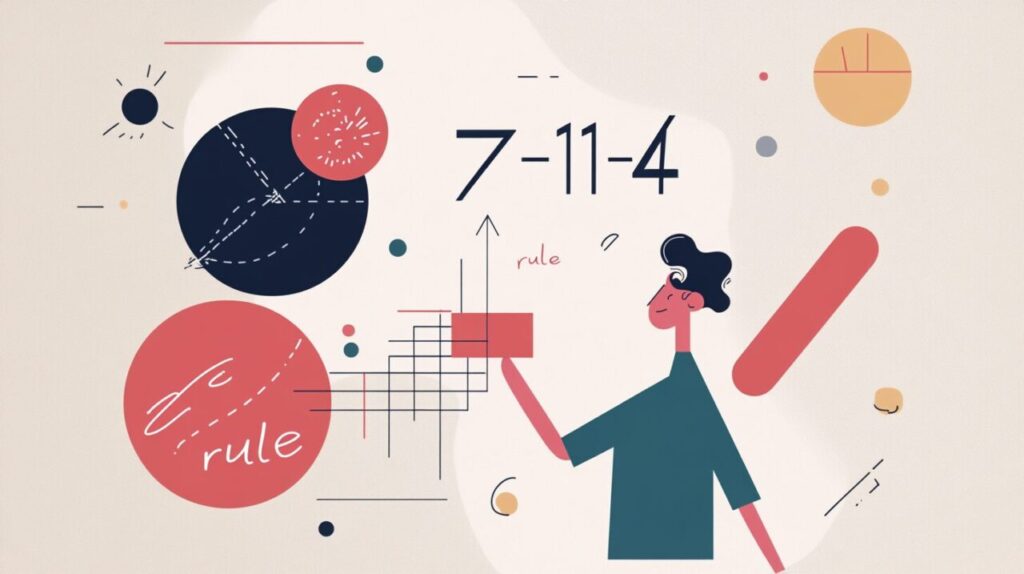
Googleが導き出した「7-11-4の法則」は、Webでの情報発信において、ユーザーとの間に強固な信頼関係を築き、最終的に成果へと結びつけるための強力な指針となります。
この法則は、ユーザーが「この人から買いたい」「この人のサービスを利用したい」と心から感じるまでに必要な、時間(7時間)、接触頻度(11回)、そして多角的な接点(4つの異なる媒体)という、人間の心理と行動に基づいた真実を教えてくれます。
多くの人がSNS単体での発信に終始したり、継続が困難になったり、あるいは一方的なコミュニケーションに陥ったりする中で、この法則を理解し実践することで、あなたは他とは一線を画す存在となるでしょう。
重要なのは、数をこなすことだけではなく、質の高い接触を意識することです。ユーザーが時間を費やしてでも見たい、何度も触れたいと思えるような、価値あるコンテンツを提供し続けること。そして、それぞれの媒体であなたの異なる側面を見せることで、より立体的な人間像を伝え、深い共感と信頼を獲得していくことです。
情報過多の現代において、ユーザーに選ばれるためには、あなたのメッセージを届けるだけにとどまらず、心に深く刻み込む必要があります。「7-11-4の法則」は、そのための具体的なロードマップを提供してくれます。ぜひ、この法則をあなたの情報発信戦略に取り入れ、長期的な視点でユーザーとの関係性を育んでいってください!