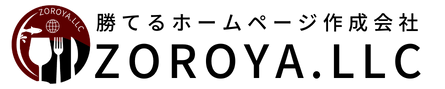※この記事にはプロモーションが含まれています
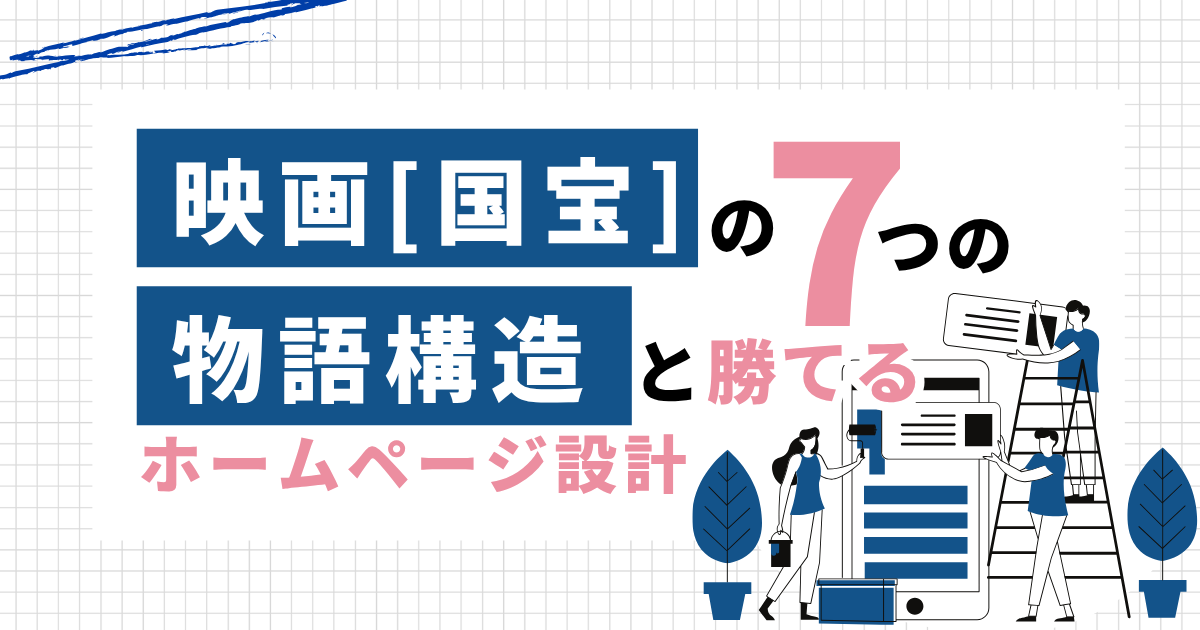
先日、話題の映画『国宝』を観に行ってきました。
ヤクザの家に生まれた少年が、ひょんなことから歌舞伎の女形としての才能を見出され、やがて歌舞伎役者の名門一家に引き取られます。芸の世界にすべてを捧げ、引き取られた家の御曹司と切磋琢磨しながら成長していく。そんな物語です。
結論から申し上げると、めちゃくちゃ良かった。
役者たちの鬼気迫る演技や、映像の艶やかな美しさ。物語全体に漂う“人間の迫力”が、観る者の胸を強く打ちました。とくに舞台のシーンで放たれる色彩と静寂の対比。美しくも妖艶な映像表現に、完全に引き込まれてしまいました。まだご覧になっていない方は、ぜひ劇場で味わっていただきたい作品です。
とはいえ、今回お伝えしたいのは『国宝』の感想ではありません。
実はこの映画には、“ヒットする作品”に共通する「物語の構造」がありました。そしてその構造は、ビジネス、とくにホームページ制作においても大いに応用できるものなのです。
映画とホームページ。一見するとまったく違うジャンルに思えるかもしれません。しかし、人の心を動かすという点では、両者は驚くほど似ています。
これからご紹介する「7つの構造」は、ホームページを通じて成果を出すための重要なヒントになります。ぜひ、最後までご覧ください。
『ヒットする映画』には共通する“物語の型”がある

「なぜ、あの映画は心を揺さぶられるのか?」
そう思ったことはありませんか?
実はヒット映画には、共通する“物語の型”が存在しています。それを証明したのが、ドナルド・ミラー氏の著書『ストーリーブランド戦略』(ダイレクト出版)で提唱されている“ストーリーブランド・フレームワーク、7つの構造”です。これは、観客や読者が自然と引き込まれるように設計されたシナリオ構造で、多くのヒット作品に共通して見られるパターンとなっています。
具体的には、以下の7つのステップで構成されています。
1.主人公の登場
2.問題の顕在化
3.導き手の登場
4.計画の提示
5.行動喚起
6.回避したい失敗
7.成功する結末
この構造は、一つひとつが意味を持っており、物語に没入する上で不可欠な要素です。
たとえば、観客はまず「自分ごと」として物語に共感するために、“主人公”の存在が必要です。そしてその主人公が何かしらの“問題”に直面していることで、興味が生まれ、引き込まれます。
そこに“導き手”が登場し、“解決のための計画”を提示することで、物語は大きく動き出します。主人公が何かしら決断せざるを得ない“行動喚起”がなされ、“失敗”というリスクや恐れが見えたとき、観客は主人公と共に緊張感を持って、成功に向かうクライマックスでカタルシスを得るわけです。
この流れが、人の感情を自然に揺さぶる“型”として、多くのストーリーに共通しているんですね。
スパイダーマンに見る、7つの構造の具体例
「7つの構造って、本当に映画に当てはまるの?」と思われたことでしょう。
僕もドナルド・ミラー氏の著書に接したときは、そうでした。しかし、大ヒットする映画というのはほとんどが、構造的にあてはまっていたのです。
たとえば、映画『スパイダーマン』を事例として、”7つの構造”に当てはめてみましょう。
1.主人公の登場
主人公ピーター・パーカーは、ごく普通の高校生です。気が弱く、目立たない存在でしたが、ある日、学校の科学実験で遺伝子操作されたクモに噛まれたことをきっかけに、驚異的な能力を手に入れます。
2.問題の顕在化
壁を登る、クモの糸を出す、スパイダーセンスで危険を察知する──そんな特殊能力を得たピーターですが、当初はそれを自己中心的に使ってしまい、彼の育ての親である叔父さんが強盗に襲われたとき、助けられなかった、という経験をします。
3.導き手の登場
導き手は、その育ての親であるベンおじさんです。「大いなる力には、大いなる責任が伴う」。叔父さんが残したこの言葉が、後にピーターの人生と使命を決定づける信念となります。
4.計画の提示
叔父を失ったことで、「力を正しく使わなければならない」と心に誓ったピーターは、スパイダーマンとして生きる覚悟を持ちます。悪と戦うことで、自らの責任を果たそうとする姿勢が計画として提示されます。
5.行動喚起
実際に街の平和を守るため、スパイダーマンとして活動を始めます。その過程においては戦いだけでなく、親友ハリーや恋心を抱くメリー・ジェーンとの関係にも悩みながら、ヒーローとして成長していきます。
6.回避したい失敗
最大の脅威となったのは、親友ハリーの父であり、自身のメンターでもあったノーマン・オズボーンが変貌した悪役「グリーン・ゴブリン」。正体を知られ、愛する人たちを危険にさらす中で、ピーターは「大切な人を失うことの恐怖」と向き合わざるを得ません。
7.成功する結末
クライマックスでは、スパイダーマンがグリーン・ゴブリンと激突します。愛する人々を守るため、すべてをかけて戦う姿が描かれ、ヒーローとしての責任と覚悟が浮き彫りになります。最終的に、彼は“選ばれた力”と向き合い、スパイダーマンとしての人生を歩む決意を固めるのです。
どうでしょうか?
この7つの構造が、大ヒットする映画に共通する構造として機能していることが分かります。観客はピーターの葛藤に共感し、つらい経験や失敗に胸を痛め、結末の勝利に感動する。まるで自分のことのように感情が動かされてしまうのです。
※ネタバレ注意※ 映画『国宝』にも当てはまる“7つの構造”
映画『国宝』は、任侠一家に生まれた主人公・立花喜久雄の人生を描いた重厚な人間ドラマです。『スパイダーマン』のような、ヒーローものアクションとは、まったくジャンルは異なりますよね。でも、物語の構造を見てみると、その展開はまさに「ストーリーブランド戦略」の“7つの構造”に沿って展開されていました。
実際にどう当てはまっていたのか、順を追って見ていきましょう。
1.主人公の登場
主人公は、立花喜久雄。(顔面国宝といわれた吉沢亮さんが演じています)彼は、ヤクザの家に生まれ、15歳のとき、父親を抗争で失い、人生が大きく動き出します。
2.問題の顕在化
血縁のない喜久雄は、才能を見込まれて歌舞伎の名門一家、花井家に引き取られました。喜久雄は御曹司、花井俊介と切磋琢磨しながら芸を磨いていくものの、才能があるがゆえに、嫉妬や不和を生み、「血のつながりがない」ことに苦しみます。そして「芸に生きる」ことにを選んだ結果、友情や愛情に亀裂が入っていくことになります。
3.導き手の登場
喜久雄にとっての導き手は、喜久雄を引き取った花井半二郎や人間国宝・万菊といった芸の先人たちです。半次郎は親の代わりを務めながら、血のつながりのない喜久雄に芸が人を助けることを伝えます。万菊は、その演舞を通して、喜久雄に芸の道を究めた果ての世界を、かいま見せます。
4.計画の提示
喜久雄は導き手との出会いから「日本一の女形になる」という夢を抱くようになります。そんな中、自ら望んで得た機会ではないものの、花井半次郎の代役として舞台に立つことになったことで、その計画が現実味を帯び始めます。
5.行動喚起
大舞台に立ち続けるなかで、喜久雄は迷いながらも芸を極める道を選び、現実との折り合いをつけながら自らを成長させていきます。
6.回避したい失敗
最大の試練は、俊介との関係でした。家族同然に育った者同士の確執。血のつながりがないことへの劣等感。そして俊介の心と身体が壊れていく様を、喜久雄は止められず、自身の選択が引き起こした“喪失”に苦しみます。それぞれの人生の選択が交錯し、立場が反転していくさまが、実にリアルに描かれます。
7.成功する結末
最終的に、喜久雄は「人間国宝」となり、日本一の女形になるという夢をはたしました。その舞台で見た景色の美しさが、彼がもとめたすべてだったのか、どうなのか。物語は受け取り手に取っては微妙に異なる余韻を残して幕を閉じます。
このように『国宝』の物語構造も、”7つの構造”をしっかり内包していたんですね。
思い返してみると、よく知るヒット映画の多くに、この7つの構造があることが分かってきます。『ラストサムライ』も『ゴジラ-1.0』『パイレーツ・オブ・カリビアン』も。乱暴な言い方に聞こえるかもしれませんが、ストーリーの構造は同じなんですよね。
そして、この構造こそ、僕たちがホームページやLPをつくるうえでの設計思想に応用できるヒントに満ちているのです。
“物語の型”は、ホームページ制作にも応用できる

さて、ここからが本題です。
先ほどご紹介した大ヒット映画に共通する「7つの物語構造」。これは、映画の脚本だけでなく、ホームページ制作にもそのまま応用できる型なんです。
特に当社では「勝てるホームページ」といっていますが、“成果を出すためのサイト”では、この構造がとても重要になります。多くのホームページやLP(ランディングページ)は、この構造から外れているがゆえに、失敗しているケースも少なくありません。
たとえば、もっともよく陥りがちな間違いは「自社が主人公になってしまっている」というもの。
会社の歴史、代表の想い、受賞歴、こだわり……。もちろん、それらはとても大事です。決して無意味ではありません。しかし、最初からそればかり語ってしまうと、見込み客はこう思ってしまいます。
「で、私に何の関係があるの?」
そうなんです。ホームページを訪れてきた人にとって最も関心があるのは、自分の問題が解決できるかどうかです。その商品サービスを通して、自分はどんな変化を得られるのか、どんな未来を実現できるのか、それを知りたいわけです。
つまり、売り手が主人公になるのではなく、顧客を主人公として、メッセージもデザインも考えるべきなんです。では、売り手は、どういうポジションに立てば良いのかというと、”導き手”です。顧客が抱える悩みや不安、問題を、売り手がどどのように問題解決するのか、その計画と、行動喚起を明快に提示する必要があります。
売り手は”主人公”ではなく、”導き手”であるべき
考えてみてください。スパイダーマンで、ベンおじさんが主人公だったら、映画としては成立しませんよね。誰も観たくない。でも、多くの企業のホームページは、まさにその「ベンおじさん型」になってしまっているわけです。自社の話ばかりで、顧客の物語が見えない。だから、誰の心にも響きません。成果も出ない。
逆に言えば、見込み客を“主人公”に設定し、自社を“導き手”として配置すれば、ストーリーは一気に力を持ちます。たとえば、「あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?」と問いかけるのは、顧客を主人公にする良い手段ですね。それから、その悩みに解決策を示すことや、他のお客様の声を通して、自分も同じように問題を解決できるかもしれないと感じてもらうこと、それから、その悩みを解決しなかったときのリスクについて教えてあげるのも、導き手の役割です。
“ストーリーブランド・フレームワークの7つの構造”を内包するホームページが、成果の出やすい設計になるのは当然ですよね。
この構造を使うことで、見込み客は自分のこととして情報を受け取り、自然と行動へと向かいます。だから売り込まなくても売れる。説得しなくても伝わる。共感が先に立つからこそ、反応がまったく違ってくるのです。
ホームページに「7つの構造」を応用する具体的方法
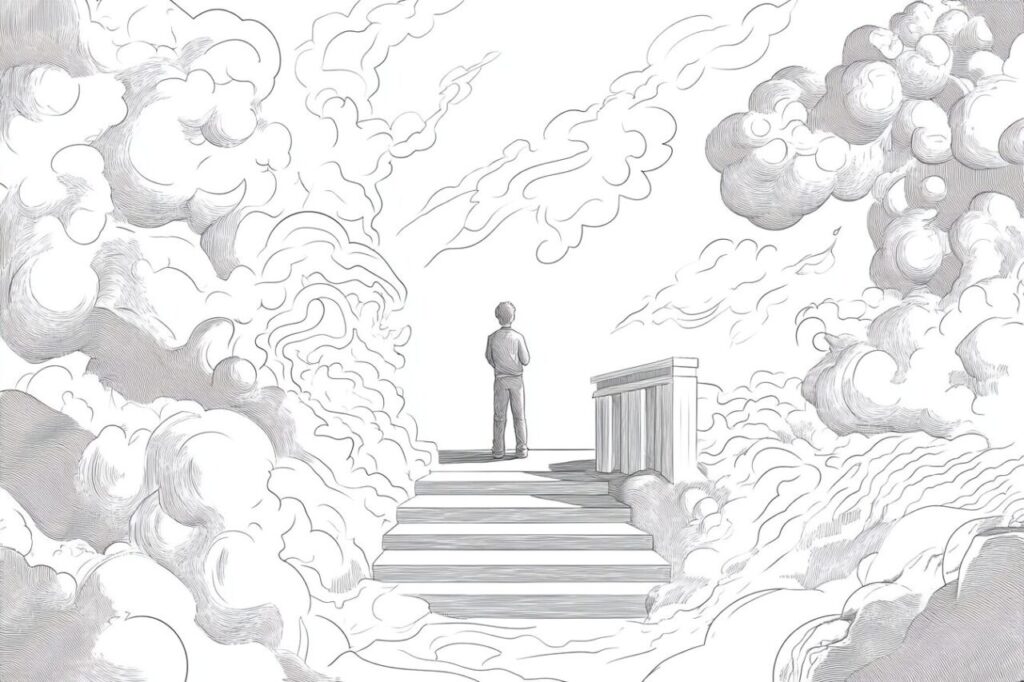
それでは、大ヒット映画に共通する7つの物語構造をホームページ制作に活かす具体的な方法をご紹介しましょう。各構造をどのようにサイト設計に落とし込むのか、実例を交えながら解説していきますね。
1. 主人公の登場:「ターゲットの定義」で顧客を主役に
ホームページにおける「主人公」とは、あなたの商品・サービスを必要としている見込み客です。この主人公を明確にするために、まずはターゲットの定義から始めましょう。
そして、そのターゲットが抱える問題が解決したとき、どんな未来になるのか、わかりやすく表現した言葉を、トップページ冒頭に記載するのがおすすめです。たとえば、「毎日の家事や仕事に追われて、自分の時間が全く取れないママ」をターゲットにして、オンラインで『片づけ講座』を売るなら、こんなコピーはどうでしょうか?
ゴロ寝できる時間=人生の余裕
~1日10分のワークで、1か月後、2倍の時間を手に入れよう~
顧客が主人公ではないメッセージというのは、たとえば「私は10年間、片づけ講座で2055人の人生を変えてきました」というもの。凄い実績なので、伝えないともったいない、と感じるかもしれません。もちろん、その通りです。ただ、伝える順番が違う、ということです。”導き手”としてその資格があると伝えるときに、伝えるのが最も効果的です。
なお、広告からの流入を想定したランディングページで、トップページに補足的に記載するのは良いと思います。ただ、自社の実績や主張をメインメッセージにするのはお勧めできません。
また、以下のような、見込み客が主人公であることの環境設定をしておくと、より「自分ごと」と感じられやすくなります。
- ヘッダー直下に「こんなお悩みはありませんか?」という問いかけを配置
- ターゲットとなる人物像を具体的に想像し、その人の言葉で語りかける
- 「30代の子育て世代のお母さん」「売上に悩む中小企業の経営者」など、具体的な人物像をコアターゲットとして設定
※ターゲットの定義についてはそれだけで膨大な説明を要するので、下記の記事もあわせて参考いただけると幸いです。
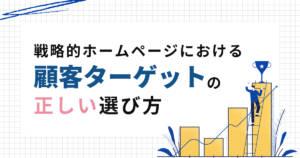
2. 問題の顕在化:「痛み」を共感的に描く
主人公(見込み客)が抱える問題を、共感的かつ具体的に描写します。ドナルド・ミラー氏の『ストーリー・ブランド戦略』では、「外的問題」「内的問題」「哲学的問題」の3つに分別して言語化することが推奨されています。
たとえば、先ほどの「毎日の家事や仕事に追われて、自分の時間が全く取れないママ」であれば、下記のような感じでしょうか。
【外的問題】
✓ 残業続きで子どもとの時間が取れない
✓ 家事効率が上がらず、いつも時間に追われている
✓ 旦那も朝から晩まで仕事でワンオペ状態
【内的問題】
✓ このまま働き続けて、体調を崩すのではないかと不安
✓ 子どもに申し訳ない気持ちでいっぱい
✓ たまには昼間からゴロゴロしたい
【哲学的問題】
✓ 本当に大切なものを犠牲にしてまで働く意味があるのか?
✓ かといって、家事や子育てをおろそかにしたら母親失格では?
ページへの反映事例
ページ構成では問題提起セクションを設けて、3つの問題を段階的に提示していくのがおすすめです。
この順で深掘りしていく構成にすることで、見込み客は表面的な悩みから心の奥にある本質的な問題まで、自然と自分自身と向き合うことができます。
視覚的な表現では、チェックボックス形式で複数の悩みを列挙し、見込み客が「まさに私のこと!」と感じられるようにするのが効果的。吹き出しやイラストを使ってターゲットの心の声を表現したり、グラフや統計データで問題の深刻さを客観的に裏付けることで、感情と論理の両面から訴求できるでしょう。
文章での表現テクニックとしては、「夜10時に帰宅して、散らかったリビングを見てため息…」といった具体的なシチュエーションを描写したり、「本当はもっと子どもと遊んであげたいのに…」など読者の心の声を代弁する表現を織り交ぜることで、より深い共感を生み出せると思います。
注意点としては、ただ問題を羅列するだけでなく、それぞれがどう関連しているかストーリー性を持たせること。ネガティブになりすぎず、「きっと解決できる」という希望も暗示することで、見込み客が期待を抱けるようにします。ターゲット外の属性の人が読んでも「この人たちは大変だな」と共感できるレベルに調整できると、より多くの人に響くメッセージになります。
3. 導き手の登場:「信頼できる専門家」としてのポジショニング
ここで初めて、あなた自身や自社を“導き手”として登場させます。
すでに見込み客は、主人公として問題を抱えており、その解決を願っている状態です。導き手の役割は、見込み客の苦悩を理解し、共感しつつ、安心して任せられる「信頼できる存在」であることを伝えること。
導き手の信頼を築くための特性
ドナルド・ミラー氏は、導き手の信頼を高めるには以下の2つの特性が必要だと述べています。
- 共感:
見込み客の内的問題や哲学的問題を理解していること。 - 導き手としての資格:
見込み客の問題を解決できる解決策、対策を持っていて、それを裏付ける証拠や実績、権威性がある。
たとえば、わかりやすいのは、以下のような文脈を、メッセージ文に組み込むことです。
私も過去、同じように時間に追われ、自分のことが後回しになっていた時期がありました。そんな時に出会った整理術を、今では2055人の受講者に届けています。
このように、共感の言葉+実績や経験の提示をセットで伝えることで、売りつけるだけの存在ではなく、親身に寄り添ってくれる「導き手」としてのポジショニングができます。
実績やお客様の声の見せ方にも注意
ありがちな失敗は、権威性ばかりを前面に出してしまうことです。
「創業30年、〇〇賞受賞、メディア掲載実績多数…」などの情報はもちろん重要ですが、それ以上に、「自分と似たような人が、ちゃんと結果を出せたのか?」が判断基準になります。
そのため、「導き手」のセクションでは、実績よりも、実際の声やリアルな実績、ストーリーを意識的に配置しましょう。以下に事例を挙げておきます。
- 初心者の方でも成果が出せたお客様のインタビュー事例
- 年齢や境遇が近い方の体験談(ビフォーアフター)
- ブランドが成り立つまでのストーリー(なぜこの事業をはじめたのかなど)
- 代表がどんな苦労、失敗を重ねて、今のノウハウに辿りついたか
- 顧客の声を、感情的な変化にフォーカスしてストーリーで紹介
4. 計画の提示:「解決への道筋」を明確に
導き手として、問題解決のための具体的な計画を提示します。この計画は、複雑すぎず、実現可能性が感じられるものでなければなりません。
ホームページへの具体的な反映事例としては、以下のようなものが考えられます。
- 3〜5ステップの簡潔な流れを提示
- 各ステップで何が起こるのかを具体的に説明
- 図やイラストを使って視覚的に理解しやすくする
- 他との違いを視覚的に表現できるとなおよい
- 初回は無料相談でOKなど、最初のステップを小さくする
見込み客が迷うのは、「やってみたいけど、難しそう」「面倒くさそう」と感じるときです。そこで、導き手として、シンプルな手順、かんたんに出来そうなイメージで「この通り進めていけば大丈夫」と安心させてあげるわけです。
5. 行動喚起:「今すぐ行動する理由」を作る
次は、見込み客に具体的な行動を促す部分です。
ここでのコツは、見込み客が行動するための「言い訳」を用意してあげること。理由をつけられるなら、「○月○日まで」と締め切りを設けたり、「在庫あと○個」のように希少性を演出するテクニックも効果的です。また、商品・サービスを通して得られるベネフィットをまとめて提示するのも良いでしょう。
行動喚起の具体例
この段階は、細かなテクニックでいくらでも応用可能なので、いくつか、事例を挙げておきますね。
①期限・数量による「今しかない」訴求
例:期間限定キャンペーン
7月31日(木)までにご相談いただいた方限定で、通常3万円の「戦略設計レポート」を無料でプレゼント!
例:定員制サービス
【残り2枠】現在、制作のご相談は月に3件までとさせていただいております。次回募集は9月以降になる可能性があります。
②心理的ハードルを下げる
例:無料 or お試し制度
まずは30分の無料ZOOM相談から、気軽にお話ししませんか?
ご相談いただいたからといって、無理に売り込むことはありません。
例:返金保証 or 成果保証
万が一、ご満足いただけない場合は全額返金いたします。
あなたにとって“価値ある一歩”になることをお約束します。
③ベネフィットの再提示 + CTA
例:行動の先にある変化を明示
このページから申し込めば──
✅ 売れるサイトの構成がわかる
✅ お客様に「この人だ」と選ばれるようになる
✅ 営業ゼロでも、自然と仕事が舞い込む流れがつくれるあなたも「勝てるホームページ」の第一歩、踏み出してみませんか?
④「失うものは何もない」と思わせる文言
例:気軽さと選択権の明示
もし内容が合わなければ、お断りいただいても構いません。
まずは、あなたのビジネスにどんな可能性があるか、確認してみてください。
行動喚起については、細かなテクニックがたくさんありますので、他の文献やメディアも参考にしてみてください。
6. 回避したい失敗:「行動しないリスク」を提示
このまま問題を放置した場合に起こりうる失敗やリスクを、エモーショナルに訴える部分です。
人の脳は、何かを得る喜びより何かを失う損失の方を2倍過大評価します。「損失回避の法則」といわれますが、生物学的にプログラムされたこの法則が働くため、この部分は非常に効果的です。スパイダーマンも、自分の大好きな女の子を失いたくないから、強敵に挑むのです。
ただし、恐怖心を煽るのではなく、現実的な問題として提示することが大切です。
「行動しないリスク」を伝える表現バリエーション
いくつか、よくランディングページで使われる事例をご紹介しましょう。
①ストーリーテリング形式の事例
あなたには、今、2つの選択肢があります。
ひとつは──「今は忙しいから」「あとでやればいい」と、このまま何もしないという選択。
たしかに、大きな変化はないかもしれません。けれど、気づかないうちに、あなたの代わりに誰かが“選ばれて”いきます。何かが壊れるわけではない。ただ、あなたのことが思い出されなくなるだけです。
もうひとつは──小さくても、今ここで一歩を踏み出すという選択。
ホームページを見直す。「伝える順番」を変えてみる。たったそれだけで、信頼が生まれ、反応が変わる可能性があります。どちらを選んでも、きっと明日の生活はあまり変わらない。
でも、半年後、1年後に手にしている未来は、まったく違っているはずです。
②数字とデータで現実を突きつける事例
失うのはお金ではなく、二度と出会えないチャンスです!
- ホームページ経由で月10件の問い合わせがある企業と、ゼロ件の企業。当然ながら、1年で120件の差がつきます。
- 1件10万円の商品なら、それだけで年商1200万円。
- その差は、商品の魅力?広告費?…いいえ、今すぐ「伝える構成」を変えることにあるんです。
③追伸メッセージとして、そっと背中を押す事例
今、行動を起こさなくても、大きなトラブルが起きるわけじゃない。
急激に売上が落ちるわけでもない。でも、気づかぬうちに、少しずつ、選ばれなくなっていく。
- 検索評価が上がらない
- 問い合わせが来ない
- 紹介も減っていく
- 時代遅れと言われる
何も変化していないのに、いや、変化していないからこそ、選ばれなくなっていきます。そうなる前に一度、私たちにご相談ください。
なお、このパートは、ページ下だけでなく、ファーストビューの下に持ってきても効果的です。もちろん内容や表現形式にもよりますが、画像や、動画も含めて、工夫すると良いでしょう。
7. 成功する結末:「理想の未来」を描く
見込み客は、今まさに課題や不安を抱えながら、ホームページを見ています。
見込み客にとっての「理想の未来」が、“自分事”として想像できるかどうかで、成約率は大きく変わります。できるだけ具体的な映像や体験描写として伝えることで、「私もそうなれるかもしれない」と希望を持ってもらいましょう。
ここは感情的に訴えた方が成果の出やすい部分なので、数値的な成果だけでなく、エモーショナルな変化も含めて表現してください。
映像描写型(視覚、聴覚に訴える)
以下のようなショートムービー、漫画、イメージ動画を制作しても良いかもしれません。
想像してみてください。朝、目覚ましよりも少し早く自然に目が覚める。
お気に入りのマグカップでコーヒーを飲みながら、スマホを見ると──
1件の問い合わせ通知。
そしてその後、毎週のように理想のお客様からの依頼が入る。
無理に売り込まなくても、「この人にお願いしたい」と選ばれるようになる。
価格で比較されることもなく、あなたらしい提案が評価されるようになる。
そんな日々が、もし“ホームページを変えるだけ”で手に入るとしたら、どうでしょう?
ビフォーアフター型(変化の明示)
ビフォーアフターは、見込み客の問題を解決できる示し方として様々な業界で万能です。
Before
× SNSを更新しても反応が薄い
× ホームページからの問い合わせは月0〜1件
× 誰に向けて伝えているのか、自分でも分からない状態
After(3ヶ月後)
〇 ターゲットが絞れたことで、LPの反応率が2倍に
〇 理想のお客様から指名で申し込みが入る
〇 営業しなくても、仕事が“向こうからやってくる”ように
変えたのは、「伝える順番」と「構造」だけ。でもその変化は、想像以上に大きな差を生みます。
顧客の証言風(リアルな感情表現)
お客様の声として上手に表現できると強いですね。動画インタビューや、雑誌風の記事にするとあらゆる業界で効果的です。
「ほんの少し、構成を変えただけだったのに──」
そう語ってくれたのは、サービス業を営む30代女性のAさん。
それまで1年で数件しか来なかった問い合わせが、たった1ヶ月で5件に。
しかも、理想通りのお客様ばかりだったそうです。「今は、自信を持って“うちはこういう人のためにあるサービスです”って言えるようになりました。あの時、行動して本当によかったと思います。」
まとめ

映画『国宝』や『スパイダーマン』『ラストサムライ』などヒット映画の物語構造には、「勝てるホームページ」と共通する“7つの構造”が存在していました。
ヒット映画が人の心を動かすように、ホームページも、主人公=見込み客、導き手=自社という立ち位置を明確にし、「問題の提示→解決の計画→行動喚起→成功の未来」をストーリーとして描けば、自然と共感と信頼が生まれ、反応が変わっていきます。
こうした設計の仕方をすることで、選ばれる確率は確実に高くなるでしょう。もし今あなたのホームページが、成果につながっていないと感じているなら、現在のWEBサイトは、主人公が“あなた自身”になっているのかもしれません。顧客こそが主役であり、私たちはその導き手。そんな視点から、ホームページの「物語構造」を見直してみてはいかがでしょうか。